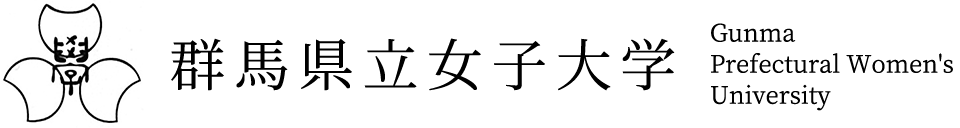令和6年度公開講座概要
生成的AIの現状と応用
開講日時 9月3日(火) 13時00分~14時30分
生成的AIという革新的な技術発展により、AI(人工知能)が私たちの生活に大きくかかわってきています。本講義ではAIの仕組みとAI研究における難しさについて分かりやすくお話しします。そして我々が研究を進める医療と介護分野での応用を例にAIの可能性と課題について紹介します。
担当教員 文学部文化情報学科 教授 神崎 享子
社会調査とは何か―社会を正しく知るために―
開講日時 9月3日(火) 14時40分~16時10分
社会を正しく知るための方法の一つである社会調査について、そのさまざまな形態を紹介します。また、この中からサーベイリサーチのしくみについて解説します。サーベイリサーチは、明らかにしたい集団(母集団)から一部の人びとを取り出して調査する標本調査です。なぜ一部の人びとにたいする1回の調査で母集団のことがわかるのでしょうか。一緒に考えてみましょう。
担当教員 文学部文化情報学科 准教授 歸山 亜紀
いけばなと風景
開講日時 9月5日(木) 13時00分~14時30分
人は自然の風景に感動し、その感動をさまざまな芸術ジャンルを通じて表現することを試み続けてきました。その一つに、いけばなによる風景の表現があります。この講義では、風景をめぐる美学的思想の伝統を参照しながら、小原流の「写景盛花」における風景の表現の特色について考えます。
担当教員 文学部美学美術史学科 講師 青田 麻未
名画にアクセス!トレースで作品を味わおう。
開講日時 9月5日(木) 14時40分~16時10分
名画を観るのではなく、「写(トレース)して、味わう」ことを体験していただきます。誰もが一度は見たことのあるピカソやシャガール、ミュシャなどの作品からお気に入りの一枚を選び、トレーシングぺーパーに写してみましょう。美術館でも行った大人のための大好評企画です。楽しくてリフレッシュできること間違いなし!
担当教員 文学部美学美術史学科 准教授 奥西 麻由子
なぜ英語は難しいのか?:第二言語習得論のアプローチ
開講日時 9月7日(土) 13時00分~14時30分
母語は誰でも苦労なく身につけることができるのに、なぜ外国語の習得は難しく、成功する人と失敗する人がいるのでしょうか。本講座では、外国語習得のプロセスやメカニズムを解明しようとする学問である第二言語習得論からこの問題を考えます。
担当教員 文学部英米文化学科 教授 飯村 英樹
海を渡る情報と郵便―帆船時代のアメリカを例に―
開講日時 9月7日(土) 14時40分~16時10分
帆船の時代には、海の向こうから情報を得たり、遠方に暮らす親族や知人と手紙をやり取りしたりするには、長い時間だけでなく様々な困難が伴いました。この講座では、イギリスの植民地だった17・18世紀のアメリカを例に、帆船が運んだ情報の特徴や、帆船を介した当時の郵便サービスの実情を紹介します。主な手掛かりとして、同時代の新聞記事を用います。
担当教員 文学部英米文化学科 准教授 笠井 俊和
『万葉集』入門
開講日時 9月10日(火) 13時00分~14時30分
『万葉集』は、飛鳥時代後期から奈良時代前期までの歌を集めた現存最古の歌集です。近年では元号「令和」の典拠となったことでにわかに注目を浴びましたが、実のところどういう書物なのかということは案外知られていないかもしれません。この講座では、『万葉集』の概要をお話ししたいと思っています。
担当教員 文学部国文学科 准教授 鈴木 崇大
『紫式部日記』を読む
開講日時 9月10日(火) 14時40分~16時10分
紫式部によって書かれた『紫式部日記』は、宮仕えの記録という側面を持ちます。『源氏物語』に関わる出来事や藤原道長とのやり取りをはじめ、一条天皇の中宮である藤原彰子の女房としての出仕の日々が記されています。『紫式部日記』の記述を読み解くことによって、さまざまな紫式部の姿について考えてみたいと思います。
担当教員 文学部国文学科 講師 佐藤 洋美
世界の動きを理解するために―国際関係における対立と協調―
開講日時 9月12日(木) 13時00分~14時30分
私たちが暮らす社会とは異なり、世界には安全や福祉などを主権国家に提供する機関は存在しません。そのため、国家は「自分の面倒を自分で見る」ことを原則として行動しなければなりません。それが時には対立を生み出したり、協調関係につながったりすることもあります。この講座では、こうした国際関係のパターンを解説します。
担当教員 国際コミュニケーション学部グローバル社会システム課程 教授 野口 和彦
国際法による紛争解決
開講日時 9月12日(木) 14時40分~16時10分
国内社会に国内法があるように、国際社会にも関税や輸出規制などの貿易、地球環境の保護、国際犯罪、武力紛争など国境を越えた事柄に対応するために国際法というルールがあります。この講義では時事的な話題を取り上げながら、国家間でのもめごと(これを「国際紛争」と呼びます)と、それらに対し国際法を用いた解決手段としてどのようなものがあるのか、ということを説明します。
担当教員 国際コミュニケーション学部グローバル社会システム課程 講師 鈴木 悠
「難民」は、20世紀以前には存在しなかった!?
開講日時 9月14日(土) 13時00分~14時30分
「20世紀以前には難民は存在しなかった」と言うと、非常に奇妙に聞こえるかもしれません。人々が住む場所を追われ移動を強いられるという現象は、いつの時代にもどの国においても繰り返されてきた歴史です。にもかかわらず、20世紀以前に「難民」は存在しなかった。その意味を考えます。
担当教員 国際コミュニケーション学部グローバル社会システム課程 准教授 山岡 健次郎
上杉謙信が利根川端の陣で「佐藤のバカ!」と激高した超難解な書状を読む
開講日時 9月14日(土) 14時40分~16時10分
天正2年(1574)4月、上杉謙信は現在の明和町大輪の利根川端に陣を張っていました。宿敵北条氏政に包囲されている対岸の羽生城を救援するためです。ところが、ある日の軍議で謙信は「佐藤のバカ!」といきなり激高したのです。え!?何があったの?その時の陣内の様子をリアルに伝える超難解な謙信の書状があります。一緒に読みましょう。
担当教員 群馬学センター 教授 簗瀬 大輔
〇お問い合せ
事務局連携推進係
TEL:0270-65-8511(代表)
MAIL:renkei@mail.gpwu.ac.jp