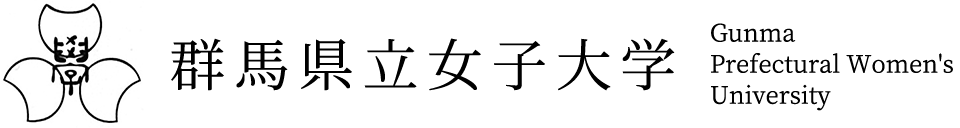広がる活動の輪
富岡賢治

群馬学連続シンポジウムの模様
上毛新聞で「群馬学ことはじめ」の欄を一年間にわたり設けていただき、県立女子大学の教授達が群馬県の言葉、文学、歴史などの研究成果の一端を次々に紹介させていただいた。学長の私は、あの教授が群馬についてこんな研究をしていたのかと驚いたり、興味深い内容に感心したりしていたが、何より群馬県で育った私が全く知らなかった事柄が次々に明らかになり、あらためて新鮮な眼で郷土群馬県が見えるような気がしたものであった。
考えてみれば、我が大学の教授達は全国から公募されて来て、それまで群馬に縁もゆかりもない人たちである。住めば都で地元に関心を持つのは当然としても、住んでいるからといって研究対象に群馬を選ぶことはない。研究対象として魅力があり、知的関心を持つものが大いにあるからなのだ。
これらの教授達が、群馬県の文化、経済、生活を幅広く多角的にとらえ直し、それを次世代に伝えていこうとする群馬学の確立を提唱する企てに積極的に参加し、幹事役を努めたいと言い出したのだ。
研究者だけでなく、ビジネス界の方々、芸術家、郷土史家等、群馬について長く勉強している県民の方々の幅広い参加により群馬学を確立していこうと提唱してから二年になる。シンポジウムも多数の県民の入場者を迎えて六回開催した。
そうすると群馬学という名称も広がって来た。「群馬学って言ってるんだってね。よくわからないけど、おもしろそうだね。」などと声をかけて来る商店主や仲間が増えて来た。私の所に見も知らぬ人から郷土の物語を自家本にしたからといって送って来る方が何人かいたり、沼田の奥で地域の物産市を頑張ってやっている青年からは、郷土食をテーマにシンポをやってくれとか言ってくるようになった。
先日、日本文化研究者として第一人者で知られる河合隼雄文化庁長官が公開授業に来学し、群馬学っておもしろいねとえらく感心し、何か応援したいと言って帰って行った。一週間程して文化庁の若い課長から、「長官から応援したいので何か考えよと指示されたがどうしましょうか。群馬学、東北学、大阪学という地域学で有名なとこが集まって東京か大阪でフォーラムでも。」と言って来た。
「言い出したのは群馬。東京や大阪で開くなんてとんでもない。群馬県で開くから、あなたは会議費だけ用意して待ってればいいよ。」と言っておいたが、さあてどうしたものかと思っている。(県立女子大学長)
とみおか・けんじ 高崎市出身。高崎高。東京大法学部卒。文部省(当時)に入り、同省生涯学習局長、国立教育研究所長、日本国際教育協会理事長などを歴任。2003年1月から県立女子大学長。
ツケアゲとテンプラ
篠木れい子

伊藤信吉著『マックラサンベ―私の方言 村ことば』(川島書店、2000年)
厳しい寒に身を縮ませる日が続いている。しかし、春はすぐそこまで。それを感じさせてくれるのが<ふきのとう>。枯れ葉をそっとよけると、小さな膨らみが。若々しい色と香りに歓声を上げて。しばし眺めて。自然の偉大なる命を感じるのは私だけではないだろう。やがて、「ふきのとうのてんぷら」となって、我が家の春待つ夕食に変身する。
ところで、伊藤信吉の上州への想いが溢れる『マックラサンベ』は、「村ことばの町体験」で始まる。その冒頭にあるのがツケアゲ。信吉(明治39年生)少年が静岡県の沼津の町のてんぷら屋の店先で、「ツケアゲを売ってクンナ」と言って店の人に奇妙がられた。これが「村言葉の町体験」「生地方言の他国体験」であったという。そのツケアゲの中身は何であったか、残念ながら記されていないが、信吉の生地群馬のそれは、センゼーバ(野菜畑)で穫れる野菜類のてんぷらであり、タマにしか食べられないご馳走であったという。 さて、ツケアゲは、人びとが「小麦粉の衣を付けて揚げたもの」と捉えたことを語る。作る動作に沿って造くられた複合語ツケアゲは、今や風前の灯火。外来語のテンプラが群馬全域を席捲しつつある。このツケアゲからテンプラへの語の変化は、単なる語の入れ替えには終わっていない。吾妻郡六合村でも70歳代からすでにテンプラである。もちろん、「ジャオーのテンプラ」も作られる。ただし、この地のこの年代のテンプラは、信吉が郷愁を覚える<ツケアゲ>ばかりでなく、言うならば<四角いドーナツ>までをもその仲間としている。それは、テンプラという語を取り入れたことで、ツケアゲの<付ける>から開放されたことによると考えられる。語形の交替が、生活世界の分類・認識の仕方にまで及ぶ好例である。なお、このお菓子のテンプラは、別名カリントを持っているが、「テンプラのカリント」と説明され、ふきのとうのように「カリントのテンプラ」とはならないことが、また、興味深い。
地域のことばと生活。それは、地域の生活文化を語ると同時に、私たちのことばの営みの普遍性をも示唆してくれるのである。(県立女子大学教授)
しのぎ・れいこ 福島県生まれ。国学院大文学部卒、東京都立大大学院人文科学研究科修了。高知女子大助教授を経て県立女子大へ。国語学専攻。現在同大教授、国文学科長。著書に「群馬の方言―方言と方言研究の魅力―」など。
中世歌人と神社
石川泰水

定家神社(高崎市下佐野町)
私の専門とする中世和歌は、残念ながら群馬の地と特に深い関わりを持つ分野ではないのだが、中世歌人の名前に由来した名称の神社が県内に少なからず存在しているのはおもしろいことだ。たとえば以前に高崎市の「佐野」について記した時に『新古今集』撰者の一人藤原定家の名を冠した定家神社に言及したが、同じ高崎市の乗附町にはやはり『新古今集』撰者で、定家とライバルのように称される藤原家隆の名に由来したらしい家隆神社というのが存在する。また、現在の高崎市役所のすぐ南には、平安時代末期の武士であり、歌人としても名高かった源頼政を祭る頼政神社があり、更に妙義神社の「妙義」の名も、南朝の後醍醐天皇に仕えた貴族で、『耕雲口伝』など和歌関係の著作を残す花山院長親の法名である明魏に基づくとも言われ、長親は妙義神社の祭神ともなっている。
この中で由来がもっとも明らかなのは頼政神社であろう。高崎藩主大河内氏の祖とされる源顕綱は頼政の孫にあたり、武人・歌人として名高い先祖を同地に祭ったのである。定家神社が佐野の地に建てられた理由も想像はできる。定家の有名な和歌の一首に
駒とめて袖うちはらふかげもなし佐野の渡りの雪の夕暮
という和歌があり、ここで詠まれた「佐野」はおそらく高崎市の佐野ではないのだが、その地名が各地に存在するために混同され、中世には前記の定家詠の「佐野」を高崎市の佐野と考える説もあったことが文献から確認される。その説が根拠なのだろう。
だが、有力とも言いがたい一説を根拠に、よりによって定家(彼はこの地を訪れたこともない)を祭神とする神社を建て、更にはその関連からか同じ新古今歌人家隆までも引っ張り出してきた、その人々の意識とはどんなものだったのか。唐突に思われるからこそ、なおさら興味深い。(県立女子大学教授)
いしかわ・やすみ 埼玉県出身。東京大卒。同大学院人文科学研究科単位取得退学。昭和61年に県立女子大学に赴任し、現在、同大教授。日本文学専攻、とくに中世和歌の研究を専門とする。著書に和歌文学大系23「式子内親王集・俊成卿女集・建礼門院右京大夫集・艶詞」(共著)。
群馬のヒガンバナ
篠木れい子

笛木直美氏撮影
春秋の彼岸が近づくとヒガンバナに想いを巡らす。この私の数年来の習わしは、『ヒガンバナが来た道』(有薗正一郎著)との出会がもたらしたもの。それは「水田稲作農耕文化を構成する要素の一つとして、縄文晩期に中国の長江下流域から日本に直接渡来した」という。結論もさることながら、それが十余年にわたる国内外の自生地踏査と文献調査によって導き出されていることに、そして、今が有史以前に繋がることに、心惹かれた。さらに『ヒガンバナの博物誌』(栗田子郎著)によって、種子を結ばぬものだけが渡来したことを知った。とすれば、稲作の伝播はヒガンバナとともにあり、ヒガンバナの旅には人びとの意志が必ずあるということになる。改めて日本文化の深層に関わる研究等の成果を読みつつ、全国のヒガンバナの方言量と分かり得た造語発想の視点から、その分布を地図に落として見た。するとそれは、隣接諸科学の研究と呼応していたのである。
ヒガンバナの方言。その数は優に五百を超えるが、その多くは西日本に集中している。食べられていたことを語る語形や、紙や壁に混ぜ込まれたこと(鼠害の防止であろう)を、あるいはまた、神事に用いられたことを語る語形もある。それに比べると、東日本は極めて少ない。にもかかわらず、群馬は、語彙量は勿論のこと、驚くほどに多くの発想による語を有している。しかも、食べた経験無くしては造りえぬ「舌曲がり」等もある。また、群馬の造語としてよい「蝿取り花(草)」(毒性を利用して蠅取りに使ったと推測される。江戸の頃の造語か)もある。九州等にある古い時代に造られたであろう語と同源と想われるものもある。加えて注目されるのは、多くの市町村史・誌がヒガンバナの方言を記していることである。共通語としてよい「彼岸花(草)」でさえ。
今なお、求める全体解明には遠い。しかし、ヒガンバナをめぐっての私の旅は、交錯する諸科学の恩恵に浴する喜びと、ことばは生活人が生活の場で紡ぎ出したものであることを実感するときめきの旅である。(県立女子大学教授)
しのぎ・れいこ 福島県生まれ。国学院大文学部卒、東京都立大大学院人文科学研究科修了。高知女子大助教授を経て県立女子大へ。国語学専攻。現在同大教授、国文学科長。著書に「群馬の方言―方言と方言研究の魅力―」など。
鏡花と上毛新聞
市川祥子
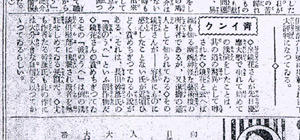
上毛新聞・大正12年5月26日第3面
大正十二年(一九二三)五月二十六日の「上毛新聞」第三面には「青インク」という欄があり(図)、以下の記事を載せる。〈◇泉鏡花さんが先日慶応大学で生まれてはじめての講演をしたことは、その道の驚異として噂された◇鏡花といえば誰も知る幽婉神怪な芸術境の所有者であるが、また潔癖の通人として知られている◇その鏡花さんが――容易にものに感心したことない氏が近頃ひどくほめちぎっている小説がある、それは、長田幹彦氏の「波のうえ」という創作物だ〉。
この講演は五月五日に行われた三田文学会主催の文芸講演会でのもの。鏡花の話(題「菎蒻小話」)は、〈まず大きな椅子を運ばせて、ちょこなんとテーブル越しに顔をのぞかせて尻をおろすと、持参の魔法瓶の酒をコップについで、ちびちびやりながら語り出した。しかしあまりに低声であるため、よっほど前列の椅子に腰掛けた者も、はっきり聞き取ることができなかったようである。時々高くなるきれぎれな言葉を聞いては、聴衆はわけもなく喝采する。・・・・・・摩耶夫人・・・・・・お釈迦さんのおっかさんですが・・・・・・悉達太子がありまして〉(五月七日「読売新聞」第六面)といった具合。聴衆の多くは鏡花が目当てで、崇拝者らしい女性の一群はこれが終わると他を聴かずに帰ってしまったという。
日頃鏡花に関心を持っているので、「青インク」を見た時、新聞社の誰かが聴きに行ったのだろうか、ほめた話をどこから聞いたのだろう、前橋の社屋で鏡花のうわさをしているなんて、と感激した。が、他日の記事と比べてよくよく考えると、これは中央から配られた出版社の宣伝。後ろの〈◇鏡花さんのほめちぎっているその「波のうえ」は例の講談
いちかわ・しょうこ 愛知県出身。早稲田大大学院文学研究科修士課程修了。現在、県立女子大専任講師。近代日本文学専攻。専門は泉鏡花。近年、群馬県出身の作家にも研究対象を広げている。
「来ない」と運動会
北川和秀

渋川方面から赤城山をのぞむ
インターネットのサイトに、群馬弁をテーマにした掲示板がある。そこでしばしば話題になるのが、「来(き)ない」という活用形である。群馬を離れて初めてこれが群馬弁であることを知ったという発言が多い。テレビなどでは通常、共通語の「来(こ)ない」という語形が使われ、「きっと君は来(こ)ない」という歌詞の歌もあるので、ちょっと意外な気がしたが、人から直接指摘されないと、なかなか気づかないものなのかもしれない。
動詞が「ない」に続くとき、語尾は、「書かない」のようにア列か、「着ない」のようにイ列か、「受けない」のようにエ列かに限られる。ところが、「来る」の下に「ない」が続くとき、共通語では「こない」という形をとる。「ない」に続く形がオ列である動詞は「来る」一語しかない。「こない」という形の方がむしろ違例なのであり、まさに変格活用である。動詞の活用はシンプルな方向に変化しているので、いずれ「こない」は「きない」に変化する可能性がある。群馬弁はそういう変化を先取りしているとも言える。
そのサイトでは、運動会における団(赤城団が赤いハチマキ、榛名団が青いハチマキ、等々)のことも話題になっていた。こういう話題は、懐かしさも加わって大いに盛り上がる。山の名は上毛三山が基本で、四団以上ある場合には、浅間、白根、武尊、三峰、子持、谷川などのどれかを加えることが多いが、山と色との組み合わせとともに変化に富んでいる。運動会のチームを山名で表すのは群馬特有の現象だと思われるが、どうであろうか。
「きない」や山名の団名が群馬特有であるのかどうかは一つの例に過ぎない。他県のことを知って初めて群馬の特徴が客観的に見えてくる。群馬出身者でないとよく分からないことはいろいろあろうが、その逆に、他県から群馬に来た者の方がよく見えることも少なくないように思う。両々相俟って、より深く群馬のことが明らかになればと願っている。(県立女子大学教授)
きたがわ・かずひで 東京都出身。学習院大卒。同大学院人文科学研究科修了。学習院大助手を経て、県立女子大へ。国語学・国文学専攻。現在、同大教授。著書に「群馬の万葉歌」など。
祥啓と上杉顕定
大石 利雄

現在の安中市板鼻字海龍寺付近
室町時代の画僧に
ところで、中山道の宿場町として名高い板鼻に、かつて海龍寺という寺があった。この地に勢力を張った関東管領上杉
大画家と言われながら、祥啓についてはまだまだ不明な点が多い。こと履歴にいたっては知られることはごくわずか。先の記事は、その数少ない貴重な史料である。この時代の関東画壇を研究している私にとって、祥啓はすでに魅力ある画家であったが、群馬の関わりを確信した今、尚更の想いを抱く。彼の眼に、群馬の自然はどう写ったのか。土地の人々との交流はどうであったのか。また改めて、顕定との関係も気になる。なぜなら顕定自身、絵を能くした武人画家の一人だからである。
戦乱の世、その顕定は永正七年(一五一〇)に越後長森原で敗死。海龍寺も今は字名として残っているのみである。(県立女子大学専任講師)
●=「王」へんに「與」。
おおいし・としお 秋田県出身。東京学芸大卒。同大学院教育学研究科修了。日本中世絵画史、とくに室町時代の水墨画を専門とする。論文に「宦南について―正宗寺蔵「飲中八仙・西園雅集図屏風」を中心に―」(「国華」第一二三五号)など。
亡き子を偲ぶ碑
濱口富士雄

左、桐生天満宮・川嶋桐華碑。右、高崎長松寺・吉村伝次郎墓碑。
子が親に先だって亡くなり、親がその供養をするいわゆる逆縁の悲しみは推し量ることができないものがあろう。したがって仏典の中でも、赤子を亡くした若き母キサー・ゴータミーの深い悲しみをブッダが救済する話は広く知られている。この逆縁を石に刻むことによって悲苦のいくぶんかを
桐生市の天満宮の境内に川嶋
また高崎市の長松寺の墓域には、十七歳で
はまぐち・ふじお 東京都出身。大東文化大卒。東京教育大大学院修士課程、大東文化大学大学院博士課程。博士(文学・筑波大学)。秋田大学助教授を経て、県立女子大学へ。中国古典学専攻。現在、同大教授。著書に「清代考拠学の思想史的研究」など。
信濃なる浅間の嶽にたつ煙
竹内正彦

『伊勢物語』(小林茂美校注、新典社、昭和50年刊)
伊勢物語は男女の恋の諸相が味わい深く語られる歌物語である。和歌を中心とした章段がそれぞれ独立しながらも全体として「昔男」の一代記の体裁をとるが、現存形態に至るまでにはいくたびかの増補があったと考えられ、その基盤には口承の「歌語り」があったとされる。「昔男」に在原業平の姿が投影されているというよりも、この物語は「業平的なるもの」が呼び込まれることによって生成したということなのだろう。
物語は男と二条后高子を思わせる女性との悲恋を語ったのち、男を東国へと向かわせる。この「あづま下り」は、三河国、駿河国、武蔵国というように東海道に沿って語られていくが、その前に浅間山を詠んだ歌が入り込んでいる。信濃なる浅間の嶽(たけ)にたつ煙をちこち人の見やはとがめぬ――。信濃国にある浅間山に立ちのぼる煙は誰でも注視するものだと、都から下ってきた男が煙をあげる浅間山を不可思議な景物として詠んだものとして一応は理解できる。ただし、東海道から浅間山は見えるはずもない。この歌がもともとは信濃地方の民謡であり、伝承歌として物語に取り込まれたと推測されるゆえんである。
この歌がその土地の民謡であるとすれば、自分の熱い恋心があの浅間の煙のようにあちらこちらの人に悟られはしまいかとする恋の歌と理解できるが、それにしてもなぜ伊勢物語はこの歌を選びとったのであろうか。この歌があることによって男の旅程の不自然さは免れないし、また、こうした民謡はこの群馬の地にもあったことであろう。
古代の旅の歌は境界を越えるときに詠まれることが多い。信濃国と上野国との間にあって噴煙を立ち上らせる「浅間の嶽」はまさに越えがたい境界を示すのにふさわしい。ここから東は異郷の地。吉永哲郎氏もこの歌にふれながら指摘しておられる(『群馬史再発見』あさを社、平成13年)が、都の人びとはそのような意識を持っていたのだろう。物語はその境界を歌によって越えさせる。「あづま下り」に語られることのない上野国は、むしろそのことによって境界を越えた男を無言のうちにつつみ込み、その漂泊の思いをかたどっているのである。(県立女子大学助教授)
たけうち・まさひこ 長野県出身。国学院大卒。同大学院文学研究科博士課程後期単位取得退学。現在、県立女子大助教授。日本文学、とくに源氏物語を主とした中古文学専攻。共編著に「源氏物語事典」(大和書房)など。
朔太郎の〈しらべ〉
戸澤義夫

現存する朔太郎の作った曲
口語体の詩に挑戦し、伝統的定型詩の韻律から生じるものとは異なった、日本語の「しらべ」を探り出し、日本の近代詩史に新局面を切り拓いた萩原朔太郎は、しかしまた、「どんなことがあつても、私は文学者には成りたくないと思つた。私の希望は音楽家になることであつた。」と述べ、実際にヴァイオリン、マンドリン、ギターと次々に弦楽器を習い、当時としては相当の腕前になり、前橋の地で、大正四年に《マンドリン倶樂部》を結成して演奏活動をかなりの期間続けている。――それがやがて群馬交響楽団の設立の一契機にもなったことは御存知の方も多いだろう。
そんな彼なら、当然、作曲にも興味を示した筈であるが、では、彼はどんなマンドリン曲を作ったのだろうか。第一四回 (一九八四年) 以来、《群馬県マンドリンフェスティバル》の審査員をお引き受けしている私には、そんな興味が生まれた。
伊藤の『ぎたる弾くひと』によれば、他の作品もあったらしいのだが、二〇〇三年に出された最新のマンドリン研究書 (有賀敏文『マンドリン物語』) によっても、現在入手できる彼の作品は、ここに示されている〈 A Weaving Girl 機織る乙女〉と〈野火〉だけであるようだ。
全く単純な旋律線からのみなるものなので、彼がプロの作曲家ではなかったことは一目で分る。しかし、その音の動かし方に、具体的言えば、二曲とも文部省唱歌や演歌が拠る「四七抜き旋法」(「ヨナヌキ」と読み、ファとシがない音階のこと) ではないこと、そして後者において、短旋法や転調に対して彼が正しい、そしてエスプリのある理解力を示していることに、彼の西洋音楽への傾倒が並々ならぬものであったことを感取できよう。
その一方で、これらの曲は、確かに単純な四七抜きではないにしても、終止する際に導音(シ) を用いていない点、そして、後者がイ短調であるとすれば終止音 (ラ) で終っていない点に、さらにまた、最初のミ-ラ-ファ-ミに、若い頃あれほど嫌った三味線音楽で使われる都節音階、そして4小節目のミ-♯ファ-ラ-ミに民謡で使われる律音階の断片を認めうる点に、十分に日本的要素を見て取ることができるのである。
詩と音楽との間で行き悩んだように、群馬と東京、即ち地方と都会の間で、そして西洋と日本の間で、さらには伝統と近代の間で揺れ動き、行き悩み抜いた彼の在り方が、ほんの少しだけ垣間見られるような気がするのは私だけだろうか。
(なお、楽譜は私が二曲とも楽譜作成ソフト《フィナーレ》で作成したもので、前者はたまたま手許にあったコピーに拠っており出典先がはっきりしない。後者は最近吉田剛士が《Best Selection vol. 1》(現代ギター社) で編曲しているものから採った。) (県立女子大学教授)
とざわ・よしお 青森県出身。東京大学文学部美学芸術学科卒。同大同学部大学院文学研究科美学芸術学専攻。博士課程中退。同大同学部同学科助手を経て県立女子大学へ。美学及び音楽美学専攻。現在同大教授。著書に『近代日本の成立』(ナカニシヤ出版 平成一七年)『精神と音楽の交響』(音楽之友社 平成九年)『芸術文化のエコロジー』(勁草書房 平成七年) 等。
朔太郎の父、密蔵と本家
杉本優

第6回群馬学連続シンポジウム「萩原朔太郎と群馬」のポスター
萩原朔太郎の父密蔵の生まれは河内の国、現在の大阪府八尾市南木の本である。八尾空港のすぐ北側だが、路地を隔てた隣が浄土真宗光蓮寺、斜め向かいが真宗大谷派仏念寺、少し離れて楠本神社と、落ちいた風情の残る界隈に萩原医院がある。
密蔵は代々続く漢方医萩原玄隆の三男で、幼名を道三といった。玄隆没後、長男玄得も腸チフスのため早逝し、次男玄碩が養子先から呼び戻されて家業を継ぐ。三男の密蔵は書生待遇、労咳に効くと評判の家伝薬の調製に追われる毎日だったという。堺県立学校の小学師範科を出て一時小学校で教鞭をとったが、明治八年一月二十四歳の時に思い立って上京した。西洋医学を学ぶためである。
漢方医から西洋医へ、時代の急変は医制にも及ぶ。明治九年一月、時の内務省は医師試験規則を発布、西洋六科の試験科目を指定した。漢方による試験の排除である。漢方医は一代限りの営業のみ許され、医家の継承ができなくなった。こうした状況下、西洋医不足への対処から、東京大学医学部は日本語で講義をおこなう別科を設置していた。密蔵は明治十四年十二月これを卒業、翌年一月群馬県立病院医員として前橋の地に赴任する。
時代の動きにうまく時機をつかむものと逸するものと。萩原本家は跡継ぎ栄次の将来を遠く群馬の地にいる密蔵に託さねばならない状態となった。さまざまな事情で人は行き交い、人はふれ合う。栄次を抜きに朔太郎の精神形成が考えられないことは言うまでもない。
県立女子大学では十二月三日(土)、群馬学連続シンポジウム第六回「萩原朔太郎と群馬」を開催する。那珂太郎氏(詩人)の基調講演と気鋭の研究者をパネリストに迎えたシンポジウムを企画している。午後一時開始。会場は本学講堂。ご来場お待ち申し上げる。(県立女子大学教授)
すぎもと・まさる 高知県出身。東京大学卒。同大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。武庫川女子大学、奈良教育大学を経て、現在、県立女子大学文学部教授。近代文学専攻。共著書に『詩う作家たち』(至文堂)など。
朔太郎とブレイク
松崎慎也

ブレイクの作品をモチーフにした、大正二年の『白樺』の表紙絵。詩「虎」の冒頭が上部に刻まれている。バーナード・リーチ作。
大正三年十二月十六日付、従兄栄次宛の手紙に、朔太郎(二十九歳)は、「貴兄はウイリアム、ブレークといふ十八世紀の大画家にして大詩人なる(神秘派の巨頭)人の絵画を御覧になられました?」「かういふ絵は或は狂人の画とも見られます、併し私は大好きです、私にはそれと同じ幻惑はないけれども偉大なる共鳴があります」と記す。
大正三年は、日本において、ブレイクの紹介が本格的に開始される年である。画期をなしたのが、雑誌『白樺』同年四月号のブレイク特集であった。図版十六点、柳宗悦による評伝などが掲載され、このイギリスの詩人・画家の全容を紹介する日本で初めての試みとなる。
朔太郎はこの『白樺』を目にしたのか。雑誌『新思潮』の同年二月号、三月号の表紙絵もブレイクであった。
幻視家ブレイクは象徴を用い、独自の神話世界を創造した。そのため難解ではあるが、現代のブレイク学にとって、もちろんそれは「狂人の画」ではなく、作品の解明は随分と進んでいる。
朔太郎は、ブレイクの絵を「怖るべき幻惑と錯覚の画」と見なし、共感を示している。手紙全体からは、この時期の朔太郎の精神が、「幻惑と錯覚」とに強く惹きつけられる状態にあったことがうかがわれる。ブレイクの後は、ムンクに触れる。ただ、ここで朔太郎が、「幻覚の天才」たちに共感を抱くのは、自らも「錯覚やハルシネーション」に襲われる、同じ不幸な人間であるという意識からのようだ。手紙の後半で従兄に告白する奇怪な幻想体験。朔太郎は「犯罪」を犯したと感じた。病む朔太郎の凄まじい苦悩が伝えられる。
この頃は、『月に吠える』に収められる詩編の執筆時期と重なる。詩人の創造する精神は霊妙である。
四ヶ月後の詩の中、朔太郎のブレイク評は、「救ふべからざる迷信に堕したもの」と変わった。「五感以外の方法」を信じぬ朔太郎の目に、ブレイクの芸術は真理から遠いものと映ったようだ。(県立女子大学助教授)
まつざき・しんや 北海道生まれ。専門はイギリス文学。論文に「キーツの『秋に』をめぐる対話」(『近代英文学への招待──形而上派からモダニズムへ』所収、北星堂書店、一九九八年)など。
萩原朔太郎と与謝蕪村
安保博史

岩波文庫版『郷愁の詩人 与謝蕪村』表紙。山下一海氏執筆の「解説」は、朔太郎が蕪村句を「普遍的な詩」として解釈・批評する意味を説く。
昭和初期、萩原朔太郎は、蕪村の句集を耽読していた。昭和四年から五年、妻との離婚争議、父の死去による家督相続問題など、現実生活のトラブルが打ち続き、「我れまさに年老いて家郷なく/妻子離散して孤独なり」(「珈琲店 酔月」〈『詩・現実』第四号・昭和六年三月〉)、「いづこに家郷はあらざるべし/汝の家郷は有らざるべし!」(「漂泊者の歌」〈『改造』昭和六年六月〉)と、〈人生の漂泊者〉としての自己意識を吐露するしかなかった朔太郎にとって、〈故郷喪失者〉与謝蕪村は、単なる学問的研究の対象ではなく、通底する詩情を有する「友」となっていた。
朔太郎は蕪村の詩的世界に自身を投影させ、自らの感懐を謳い上げていった。その営みが『郷愁の詩人与謝蕪村』(第一書房・昭和十一年刊)に結実する。彼は、旧来の蕪村観に縛られず、「より因襲のない自由な立場」(『郷愁の詩人与謝蕪村』自序)で蕪村俳諧の世界に対峙(たいじ)し、彼自らが憧憬する〈魂の故郷に対する「郷愁」〉が蕪村のポエジーの核心に存することを察知し、「遠い遠い実在への涙ぐましいあこがれ」(『青猫』〈大正十二年刊〉自序)、「或るプラトン的イデア―魂の永遠な故郷―へののすたるぢあ」(『詩の原理』〈昭和三年刊〉)のキーワードを駆使して語る朔太郎詩論をも投影させて、蕪村句をより共感的に理解しようと試みた。「蕪村」という存在は、朔太郎自身の詩人としての本質と矜持(きょうじ)を再認識させもした。朔太郎は蕪村を語りつつ、自らを語り鼓舞(こぶ)していたのである。
朔太郎は 、『郷愁の詩人与謝蕪村』の一書をもって、蕪村俳諧の「実景の写生」のような「客観的特色の背後」に「詩人その人の主観 」が存することに強く注意を促し、その詩情の本質が〈郷愁〉であることを鋭く説き明かしてくれた。見事というほかない。(県立女子大学教授)
あぼう・ひろし 愛媛県出身。中央大大学院博士課程単位取得退学。九州大谷短大助教授を経て、県立女子大へ。現在、同大教授。近世俳諧・和漢比較文学専攻。主論文に「貞享初年の新風」「龍草廬と陶淵明」「蕪村と漢文学」など。
夜汽車に託して
井村まなみ

萩原朔太郎撮影写真 利根橋と両毛線鉄橋(前橋文学館所蔵)
空気の澄んだ冬の夜、車の往来も少なくなる時刻に前橋駅から東へ伸びる両毛線を高い建物の上から見下ろすと、線路が闇に沈み、電車は空中を走るように見える。今日でも夜汽車は別世界へ導き手だ。まして街中に灯りの乏しい時代、灯りを連ねて走る汽車は、人々の目にどれほど幻想的に映っただろう。
萩原朔太郎の「夜汽車」(一九一三年、発表当時の題名は「みちゆき」)では、汽車を外から眺めるのではなく語り手が乗車している。そこが同時代の詩篇と大きく異なる。「有明のうすらあかりは/硝子戸に指のあとつめたく」。早朝の冷たい外気と車内の澱んだ空気。旅の終わりに感じる疲れと寂しさを冒頭二行に集約する。それは女性を伴った逃避行でもあった。「ふと二人かなしさに身をすりよせ/しののめちかき汽車の窓より外をながむれば」。まだ珍しかった夜汽車に女性を乗せて旅をする。二重の冒険であった。
事情はヨーロッパでも同じだ。鉄道が発達を続ける十九世紀後半、汽車という新しい乗り物を題材とする詩が山のようにつくられた。ボードレールやヴェルレーヌ、象徴派の大詩人も汽車に詩行を割いている。ただし女連れの夜汽車となると、例は限られてくる。「冬になったらぼくらは出かけよう小さなバラ色の客車に乗って」。先輩詩人たちに混じってアルチュール・ランボーが冬の汽車旅行を書きつけたのは一八七〇年。当時十六才の少年は背伸びをして、恋人と旅をしたい願いを詩にこめたのである。「きみは目を閉じるんだよ車窓に映る/夜の物影が顔をしかめるのを見ないですむように」。
異性という未知の対象を知りたい。その苦しくも強い思いに支えられて、朔太郎とランボーだけが、女性を夜の汽車で連れ出す詩を書き得た。光を乗せて闇を走る汽車。やがて夜明けに通ずる夜の線路。夜汽車は彼らにとって、女性の放つ神秘と希望に重なっていた。日本とフランス、近代化に立ち会った若い詩人たちのなかで、ふたりの感受性は確かに突出していた。だからこそ、今日の読者も共感できるのである。そうした彼らの感性は、ポピュラーソングの世界にも流れ込み、チューリップの「心の旅」のようなヒット曲を生んでいる。(県立女子大学助教授)
いむら・まなみ 東京都出身。神戸大学文学部卒。パリ第八大学にて文学博士号取得。専門は十九世紀フランス詩。一九九九年より県立女子大(助教授)。著書に「アルチュール・ランボーの『後期韻文詩』に於ける否定の詩学」。
石碑に「侠気」を見る
濱口富士雄

常福寺境内の「医師大河原君碑」
石碑は文書史料を補う役割を果たすものであり、人物碑の場合は偉人を顕彰するものが多いが、一方では史書から漏れる在野の人を後世に伝え、さらにはその建立に関わった人々の思いをも不朽にする。
榛名町上里見の常福寺の境内の片隅にちょうど百年前の明治三十七(一九〇四)年と記された「医師大河原君碑」が樹々に囲まれてひっそりと立つ。医師は群馬県人の持つ「侠気」のうちの良き側面すなわち義侠の心を一世紀も前に国際的な視野から発揮しようと志し、その業半ばに客死した。すなわち当時医学の世界にあってハンセン病を最も悲惨な病であると考え、特にハワイでは患者が多いことから渡航して療法を研究することを志し、その地で多くの名医に就いて研鑽して開業し盛況を究めた。しかしそれに満足することなくさらなる研究の意志を固めて夫妻でアメリカに出向くことにし、そのとき搭乗した汽船が座礁して沈没したが、夫妻はともに取り乱すことなく端座して死に臨んだという。
この訃報に接した友人達もこれまた「侠気」をもって、医学に対する使命感を高く維持しつつも遭難して果てた医師の無念さを思い遣り、その顕彰をとわに伝えるべく当代の一流の撰文者と書者とを求めて奔走した。すなわち碑文は、当時漢学の世界のみならず文学においても高名を馳せ、森鴎外が漢文の手ほどきを受けるべく師事し、その作品である『ヰタ・セクスアリス』にも文淵先生として登場する依田百川が担い、書はその称え方に関して諸説はあるがいわゆる明治の三筆に数えられ、また童話作家として著名な巌谷小波の父としても知られる巌谷修であり、篆額は維新の元勲の一人でもある伯爵土方久元である。実に友人達の医師に対する深い思いと遠い慮りとがこうした屈指の取り合わせによる漢文碑を実現させ、現在にいたるまで確かにその価値を減ずることなく伝えている。ちなみにこの三者による県内の漢文碑には館林市三の丸に立つ「城沼墾田之碑」がある。(県立女子大学教授)
はまぐち・ふじお 東京都出身。大東文化大卒。東京教育大大学院修士課程、大東文化大学大学院博士課程。博士(文学・筑波大学)。秋田大学助教授を経て、県立女子大学へ。中国古典学専攻。現在、同大教授。著書に「清代考拠学の思想史的研究」など。
1本のネジから近代化
日下洋右

東善寺境内の小栗忠順の胸像(『全集写真探訪ぐんま 2 歴史の散歩道2』(上毛新聞社)より)
群馬にゆかりのある印象深い人物の一人は、現在の倉淵村権田に領地を有していた小栗上野介忠順(ただまさ)(1827-68)である。小栗忠順は幕府という旧体制の重臣であったが、彼が時代を先取りした日本の将来像を構想した進取の気性に富む人物であったことは注目に値する。彼の進歩的な考え方は、アメリカ合衆国の視察が源泉になったとみてよい。幕府は1858年に結んだ日米修好通商条約の批准交換のため、60年にアメリカに派遣する使節団の実質的なリーダーとして34歳の小栗を抜擢した。
アメリカを視察して彼が衝撃を受けたのは、巨大な蒸気船を建造する先進技術であった。彼はアメリカの国力の原動力が、蒸気船を生み出す工作機械とそれを用いる工場であることを認識したのである。帰国する小栗の手には一本のネジが握られていた。巨大蒸気船の建造は、結局精密なネジを大量に生産する技術力から始まることを実感したからである。この一本のネジには、日本をアメリカのような一大工業国にしたいという彼の大望が潜んでいたとみるべきである。一本のネジから、彼は造船所こそ海に囲まれた日本の近代化と工業化を進める第一歩となることを悟ったとみてよい。1865年に小栗の主張した造船所の建設が認められ、67年に横須賀でドックの建設が開始された。建設は明治政府によって引き継がれ、小栗が新政府軍の手によって斬首された3年後の71年に、ドックはフランスの技術と援助とによって竣工した。
小栗が残した遺産は造船所だけではない。アメリカから帰国後、彼は大名を廃し、藩を郡や県に改め、大統領制を敷いて日本を近代的な統一国家にしようと構想したからである。大統領制を除けば、彼の構想はそのまま明治政府によって採り入れられた。小栗忠順こそ日本の近代化と工業化の先駆者といっても過言ではない。(県立女子大学教授)
くさか・ようすけ 北海道育ち。東京教育大学大学院修士課程修了。鳥取大学、信州大学を経て現職。アメリカ文学専攻。著書に『ヘミングウェイ―ヒロインたちの肖像』、『ヘミングウェイ―愛と女性の世界』、『ヘミングウェイの時代―短編小説を読む』など。
橘守部の源氏物語研究
竹内正彦

10月22日(土)に開催される群馬学連続シンポジウム第5回「かかあ天下再考」のポスター
江戸時代、『源氏物語』の研究はとくに国学者たちの手によって深められていった。「もののあはれ」論を展開した本居宣長はなかでも著名であるが、橘守部(たちばなもりべ)も『源氏物語』に取り組んだ国学者のひとりであり、『湖月抄別記』などの著作を残している。守部は、天明元年(一七八一)、伊勢国の生まれ。十七歳の時に江戸に出て国学を志し、武州幸手に移り住んで以来、ほとんど独学で研究に打ち込み、再び江戸に出て嘉永二年(一八四九)に没する。その間、『源氏物語』以外にも広範な研究を手がけ、のちに「天保の四大家」のひとりに数えられるまでに至る。その守部の研究生活を支えたのがとくに桐生の機業家たちであったことがすでに指摘されている。彼らは守部の門人となり、研究をはじめ生活全般を支援するとともに、なかには娘を江戸の守部のもとに遊学させ、『源氏物語』などを学ばせたものもいたという話も聞く。この時代におけるこの地域の文化的関心の高さと同時に、女子教育に対する熱心さも知られてくる。よく言われる「かかあ天下」という言辞に、たとえば、守部のもとで『源氏物語』を読んでいたこうした女性たちをも想起したとき、そこにはどのような群馬の姿が浮かびあがってくるだろうか。
来る十月二十二日(土)十三時二十分から県立女子大で開催される群馬学連続シンポジウム第五回目のテーマは「かかあ天下再考」。群馬を特徴づけることばのひとつとして用いられる「かかあ天下」をキーワードにして群馬における女性のあり方をあらためて考える。また、このテーマには、かつての群馬を知るのにとどまらず、これからの時代に生きる女性のあり方を考える視座も含まれており、きわめて興味深いものとなるにちがいない。
シンポジウムのパネラーは、落合延孝氏(群馬大学教授)、塚越裕子氏(塚越屋七兵衛社長・群馬女将の会会長)、中野紘子氏(座繰り・染織家)、藤井浩氏(上毛新聞社文化生活部長)、光野純子氏(NHK前橋放送局局長)。司会は富岡賢治(県立女子大学長)が務める。問い合わせは、県立女子大事務局(電話・〇二七〇―六五―八五一一)まで。(県立女子大学助教授)
たけうち・まさひこ 長野県出身。国学院大卒。同大学院文学研究科博士課程後期単位取得退学。現在、県立女子大助教授。日本文学、とくに源氏物語を主とした中古文学専攻。共編著に「源氏物語事典」(大和書房)など。
"交響する地域"目指して
篠木れい子

群馬県立女子大学編『群馬学連続シンポジウム 群馬学の確立にむけて』(上毛新聞社刊)
16年度より始まった群馬学連続シンポジウム。多くの皆様の協力と参加があったればこそ、まずは無事その船出を果たすことができたのだと思う。
その3回分のシンポジウムの報告書が『群馬学の確立にむけて』となって、上毛新聞社より出版された。これは、極めて意義深いことと考える。音声言語と文字言語の特徴が発揮する力はそれぞれに異なり、かつ、相補の関係にある。目的に応じて、どちらの言語で発信し、あるいは交流するのがより効果的かを思案するが、「群馬学の確立」のためにはそのいずれもの力が必要であると思うからである。
昨年度のシンポジウム参加者の延べ人数は二千を越えたとのこと。群馬に関心を抱いてる人がこれほどに多いとは。本が出版された後には、感想や群馬学の重要性について記した便りも多く届けられている。私どもと同じく、学としての群馬学にまで育てるにはどうしたらよいか、思いを巡らしている人が多いことも知り、うれしく、また、心強く。
研究や活躍の分野を越えた人びととの交流、世代を超えた人びとの交流、地域を越えた交流。これらは、すべての学の、特に、地域学の発展に大きな力となるに違いない。「群馬学の確立」に向けての基盤がすでにできつつあると思う時、県立大学の一員として、その責任の大きさを想う。尚更に、先日目にした野依良治氏の一文が心に響くのである。「さまざまな役割を演じる人達の総合的貢献なくして目標の達成はあり得ない」(『学術月報』5月号、日本学術振興会)。
17年度の連続シンポジウムは「群馬の地名」でスタートしたが、この10月22日には「かかあ天下再考」があり、12月には「萩原朔太郎と群馬」が続く。"交響する群馬"を目指して、皆様と共に確かな歩みを進めたいと願っている。(県立女子大学教授)
しのぎ・れいこ 福島県生まれ。国学院大文学部卒、東京都立大大学院人文科学研究科修了。高知女子大助教授を経て県立女子大へ。国語学専攻。現在同大教授、国文学科長。著書に「群馬の方言―方言と方言研究の魅力―」など。
歌によまれた上州名物
北川和秀

上毛野形名の妻の記事を載せる『日本書記』(版本)
上州名物といえば、空っ風と雷とかかあ天下。このうち、空っ風と雷は万葉集の東歌にすでによまれている。
空っ風をよんだ歌は、「伊香保風吹く日吹かぬ日ありと言へど吾が恋のみし時なかりけり」(三四二二番)。「伊香保」は榛名山。冬には毎日のように吹き下ろす榛名おろしだって、時には吹かない日もあるというのに、私があなたを思う恋心は止むときがない、という意。滅多に止むことがないものの代表として冬の榛名おろしがよまれている。
雷をよんだ歌は、「伊香保
かかあ天下は残念ながら上野国東歌には登場しないが、日本書紀にこんな記事がある。
舒明天皇九年(六三七)に、
形名の勝利は、ひとえにこのしっかり者の妻のお蔭である。彼女を群馬のかかあ天下の元祖と言ってしまいたくなるが、でも、かかあ天下とはそもそもどういうことだろう?
県立女子大学では「かかあ天下再考」というテーマで、群馬学連続シンポジウムを開催する。一〇月二二日(土)午後一時二〇分開会。多数のご来場を心からお待ち申し上げる。(県立女子大学教授)
きたがわ・かずひで 東京都出身。学習院大卒。同大学院人文科学研究科修了。学習院大助手を経て、県立女子大へ。国語学・国文学専攻。現在、同大教授。著書に「群馬の万葉歌」など。
県民公開授業「わたしの群馬」
権田和士

県民公開授業「わたしの群馬」
授業風景
県立女子大学では、昨年度から「群馬学連続シンポジウム」をはじめとする、「群馬学の確立」に向けた様々な取り組みを始めている。
「群馬学」は、現在の群馬県の領域にあたる土地にかつて生きた人々、また現在生きている人々が積み上げてきた、重層的な文化の総体を学ぶことを目指すもので、群馬に関するあらゆることについて、大学内外の研究成果を学生や県民の皆さんと共有していくべくスタートした事業である。この「群馬学」のコンセプトに基づいて、本学は、今年度、県民公開授業「わたしの群馬」という科目を開設した。
この授業は専門的な研究機関に所属するか否かにかかわらず、各界で活躍する方々に、それぞれの研究や社会活動での成果を、本学の学生や地域の方々に示していただきたいという思いから生まれたものである。学外の多くの先生方から御協力を得ることができ、様々な視点から群馬を見直すことができる授業となった。
授業内容は、それこそ、群馬の自然・産業・歴史・文化・思想など広範な領域にわたるものとなった。群馬の山林や川などの自然とその風景。群馬産の鉄鉱石の品質や製鉄技術。養蚕を中心とする蚕糸産業の盛衰。忘れられつつあるわらべ歌や労働歌の価値。写真に記録された群馬の民俗・風習。国定忠治と周辺の人々の動静が記された古文書。有名あるいは無名の文学者たちの多様な仕事。日本の近代思想に大きな影響を与えた群馬のキリスト者たちの言動などなど。担当教員の一人として参加したが、私にとっても「ふるさと再発見」とでもいうべき授業となり、楽しかった。
県立女子大学では、後期にも学外の先生方を迎えて県民公開授業「群馬のことばと文化」を開講する。こちらの方にも多くの県民の方々が参加してくださることを願っている。(県立女子大学助教授)
ごんだ・かずひと 群馬県尾島町(現太田市)出身。金沢大学卒。東京大学大学院人文科学研究科修了。恵泉女学園大学を経て、県立女子大へ。日本近代文学専攻。現在同大助教授。論文に「小林秀雄の再検討」など。
全国2位の芭蕉句碑
安保博史

弘中孝氏『石に刻まれた芭蕉』(智書房・平成十六年二月刊)。
貞享四年(一六八七)、
さらに、『石に刻まれた芭蕉』の群馬県編を基に近世期の芭蕉句碑・芭蕉塚の建立地マップを作ると、沼田・藤岡・高崎・前橋・伊勢崎・桐生など都市部に多くの碑が分布していることは当然だが、例えば、吾妻郡吾妻町が、「月花の愚に針たてん寒の入」(吾妻町厚田/文化年間建立)以下五基、利根郡片品村が、「蕎麦はまた花てもてなす山路哉」(片品村土出/文化九年〈一八一二〉建立)以下三基、勢多郡赤城村が、「原中やものにもつかす啼雲雀」(赤城村棚下/安永九年〈一七八〇〉建立/『諸国翁墳記』に収録)以下四基というように、群馬県の山間部においても芭蕉句碑が数多く建立されている事実は、当時の上州全体の在村文化の豊かな営みの証左として、驚きと誇りをもって注目されるのである。
群馬県全域に分布する芭蕉句碑の中には、長い間放置され叢に埋もれて廃墟同然となったものもあるが、そのように「時移り世変じて」忘れ去られた往時の文事の象徴たる句碑を「石に刻まれた俳壇史の資料」として再発見・再評価することによって、近代に連続する近世期上州の豊かな文学的土壌の実態が浮き彫りにできそうだ。芭蕉句碑からは目が離せない。(県立女子大学教授)
あぼう・ひろし 愛媛県出身。中央大大学院博士課程単位取得退学。九州大谷短大助教授を経て、県立女子大へ。現在、同大教授。近世俳諧・和漢比較文学専攻。主論文に「貞享初年の新風」「龍草廬と陶淵明」「蕪村と漢文学」など。
碓氷の紅葉
石川泰水

碓氷峠(『全集 写真探訪ぐんま 4 街道を歩く』(上毛新聞社)より。
歩を進めれば他国、振り返れば故郷。信濃国との境に位置する碓氷峠を越えて行く上野国の人々の思いは、格別のものであっただろうと想像される。『万葉集』の中に碓氷の地名は二首に用いられている。
日の暮に碓氷の山を越ゆる日はせなのが袖もさやにふらしつ
ひなくもり碓氷の坂を越えしだに妹が恋しく忘らえぬかも
連作でもないこの二首が、見送る者と旅行く者の心情を各々よく表わしているだろう。しかし、中古・中世においては碓氷を詠んだ和歌はきわめて少ない。歌枕書などは「碓氷の山」「碓氷の坂」の項目を掲げ、先の万葉歌を引用しているのだが、言わば知識の中の歌枕にとどまり、和歌の中に再生されることはほとんどなかったのである。
江戸時代になり、中山道の整備に伴ってであろう、碓氷の地は人々にとって親しいものになったようだ。特に紅葉の名所として喧伝されるようになり、碓氷の紅葉をよんだ和歌が登場するようになる。
山の名は碓氷といへどいくちしほ染めて色濃き峰の紅葉葉(千曲の真砂)
碓氷とはいつの代よりか濃き紅葉昔の人に会うて問はばや(閑度雑談)
一読して明らかなように、どちらも紅葉の色の「濃き」と地名の「碓氷」を対比したおもしろさを狙った、趣向中心の歌である。
ところで私たちは、もう一つ碓氷の紅葉の歌を知っているはずだ。高野辰之の作詞による有名な小学唱歌「紅葉」である。碓氷の山中にあった信越本線旧熊ノ平駅からの眺望に基づくというその歌詞の中に、そういえば「濃いも薄いも数ある中に」とある。掛詞かと考えたくもなるが、いや、思い過ごしであろう。(県立女子大学教授)
いしかわ・やすみ 埼玉県出身。東京大学卒。同大学院人文科学研究科単位取得退学。昭和61年に群馬県立女子大学に赴任し、現在同大教授。日本文学専攻、特に中世和歌の研究を専門とする。著書に和歌文学大系23『式子内親王集・俊成卿女集・建礼門院右京大夫集・艶詞』(共著)。
自然詩人としての村上鬼城
権田和士

伊藤信吉監修・林桂編『群馬文学全集第三巻』(群馬県立土屋文明記念文学館 一九九九年刊)。本巻には、村上鬼城・長谷川零余子の作品が収められている。
村上鬼城が世に出るに際しては、高浜虚子と大須賀乙字の二人の力によるところが大きかった。特に、『鬼城句集』(一九一七年刊)の編者でもある乙字は、その「序」において、鬼城を「何物を詠じても直に作者境涯の句となつて現はれる」と評し、芭蕉に追随し一茶を凌ぐと絶賛した。以来、鬼城を「境涯」の俳人とする評価は現在に至るまで大きくは動いていない。
冬蜂の死にどころなく歩きけり
対象に向ける凝視と同情が自己の姿へと照り返されてくるこの句は、「境涯」の俳人鬼城の代表作である。しかし、鬼城を「境涯」の俳人とばかり思っていては、この俳人の全体像を見誤るであろう。たとえば、鬼城には、次のような句がある。
雷に勝つて角振る蝸牛かな
雷雨のあがった後出てきたカタツムリの姿をユーモラスに描いていて、楽しい。この句に、貧に苦しんだ俳人の境涯を見る必要はないはずである。
同じく、夏の上州名物を詠んだ句に、よく知られている次の句がある。
雹晴れて豁然とある山河かな
それまで隠されていた大地が突如として現れ出た姿と、その姿に対する驚きが素直に表現されている句である。輝くばかりの山河に初めて接したかのように感動している作者の初々しい心を、読者は受け取ることができるだろう。
出水して雲の流るゝ大河かな
洪水の後晴れてきた空と強い風に流されている雲が川面に映る様子を捉えて、雄大である。自然の猛威にさえ美を発見する「詩人の眼」を輝かせながら、大河の岸に立っている鬼城の姿までもが眼に浮かんでくる。
「雹」と「出水」の句には、俳句という文学様式に由来するというだけではない、優れた自然詩人としての鬼城の側面を認めることができるであろう。(県立女子大学助教授)
ごんだ・かずひと 群馬県尾島町(現太田市)出身。金沢大学卒業。東京大学大学院人文科学研究科修了。恵泉女学園大学を経て、県立女子大へ。日本近代文学専攻。現在同大助教授。論文に「小林秀雄の再検討」など。
群馬と秋田で同じ紙面
市川祥子

「上毛新聞」(大正十一年四月十六日・第三面)

「秋田魁新報」(同日・第四面)
図を見較べて欲しい。上が大正十一年(一九二二)四月十六日の「上毛新聞」第三面、下が同日の「秋田魁新報」第四面。家庭欄の題字部分だけが異なり、他は文章・並べ方・カットまで同じである。両紙の家庭欄が等しくなるのは前週からで、以後も継続する。地方紙の購読者が、群馬と秋田で同じ紙面を見ていたのかと思うと嬉しくなってくるが、少し気に掛かることもある。
当時の新聞は活版印刷。活字を一つずつ並べていくわけで、一つの原稿を双方で別々に組んでいたのでは、これほどぴったりと同じにはならない。では、前日までにどこかで両方の印刷をして列車で運んだのだろうか。ずいぶんな分量でもあり、それならば、その裏面の地元の記事はどうやって刷ったのだろう。活版印刷では活字で一面を組み上げた後に、上から紙型を押しつけて逆向きの型を取り、そこに鉛を流し込んで輪転機に用いる鉛版を作る。では、どこかで題字だけを変えた両方の紙型を作り、運んだのだろうか。しかし図には入れられなかったが、この面の下段には地元の記事(上毛)と連載小説(秋田魁)とがある。高温の鉛を流す都合で紙型を切って継ぎ合わせることはできないとすれば、題字と下段の記事もあらかじめ紙型作成所に預けておいたのだろうか。また、左下の女性の画に添えられた短歌は与謝野晶子のもの。著名な作家の作品を集めて家庭欄を作り各新聞社に売るコーディネーターがいたのだろうか。
そもそも、なぜ「上毛新聞」と「秋田魁新報」なのだろう。ちなみに当時の「下野新聞」にこの家庭欄はない。謎は尽きない。(県立女子大学専任講師)
いちかわ・しょうこ 愛知県出身。早稲田大学大学院文学研究科修士課程修了。県立女子大学国文学科専任講師。近代日本文学専攻。専門は泉鏡花。近年、群馬県出身の作家にも研究対象を広げている。
朔太郎の『青猫』
杉本優

「笛」を収録している詩集『月に吠える』
朔太郎は詩集『青猫』の「序」を次のように始めている。「私の情緒は、激情といふ範疇に属しない。むしろそれはしづかな霊魂ののすたるぢやであり、かの春の夜に聴く横笛のひびきである。(略)私の真に歌はうとする者は(略)あの艶めかしい一つの情緒――春の夜に聴く横笛の音――である。それは感覚でない、激情でない。興奮でない、ただ静かに霊魂の影をながれる雲の郷愁である。遠い遠い実在への涙ぐましいあこがれである。」プラトンを援用し「霊魂の郷愁」を語る朔太郎が、「序」の他の部分でも「横笛(笛)」の語を頻出させているのが興味深い。
『月に吠える』の始発期、浄罪詩篇と呼ばれる詩群中の一篇「笛」にいくつかの草稿が残されている。「〈既に〉別れし〈彼女に〉E女に」という献辞が付けられた草稿には「ああかき鳴らす人妻琴の〈調べにあはせ〉音にも/[あはせて/つれぶき]いみぢしき笛は天にあり/〈わが恋もゑにしも失へり〉」「[わが横笛/いちじき笛]は天にあり」の詩句が見られ、別の草稿に「つゝめるごとく琴をひくきみ/あゝかきならす琴にあはせて/わが横笛は天にもあり」という一節が見える。エレナと朔太郎の交歓のイメージが、「琴」と「笛」の唱和に変換されている。浄罪詩篇として「懺悔のすがた」ゆえに「わが横笛」は天上に回収されていたが、後年丸山薫に「あの頃は夢の中でよく死んだ女に逢つた」と告白した『青猫』執筆期、「その笛の音こそ」が「艶めかしき形而上学」だと「序」に記す朔太郎の耳に、今は亡きエレナ(大正六年五月没)の面影につながる「いみじき横笛の音」が聞こえていなかったか。
「艶めかしい墓場」では「さびしげなる亡霊」との出会い、自己の「生命や肉体」の腐爛の自覚をうたう。「題のない歌」は「沈黙の墓地」に「錆びついた 恋愛鳥の木乃伊」を発見して結ばれる。それらは〈書くこと〉を手放さなかった朔太郎の極北の詩であった。(県立女子大学教授)
すぎもと・まさる 高知県出身。東京大学卒。同大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。武庫川女子大学、奈良教育大学を経て、現在、県立女子大学文学部教授。近代文学専攻。共著書に『詩う作家たち』(至文堂)など。
明治の利根川水源調査行
馬場朗

利根川本流域の山と谷について手軽に知るには、小泉共司氏の名著『奥利根の山と谷』(白山書房)が極めて有益である。
「明治二十七年九月[中略]探検隊の組織せられしを探検の嚆矢とす。その結果は成功とみるべきにあらねど霊域の俤幾分味あふに足る」。『利根郡誌』(昭和四十五年刊)に抄録されている第一回利根川水源調査報告はこのように始まる。調査隊は、群馬県技師小西文之進他十七名(道案内・人夫をいれ三十九名)から構成されていた。
藤原村より奥の、利根川の源流たる奥利根山域は特に上州側の土地の者があまり足を踏み入れぬ地域であった。『利根郡誌』には、「藤原村よりここに入りしもの十幾人という数に上りたれども一人も帰らず」、ともある。一行は、「山霊の激怒」に村民が脅えるその山域に、同じく麓の村民の迷信を乗り越え欧州アルプスの高峰を征服した西洋近代初期の登山家達のごとく、進んでわけいっていくのである。しかし、一方では、帰路の水長沢で見出した「百二十年前に見たり人ありと傅ふる所の文珠岩[文珠観音]」の御利益で一行の人夫の病がたちまち癒えたことがまことしやかに報告されてもいる。群馬県山岳史の黄金期たる谷川・一の倉沢の開拓が(清水トンネル開通と相前後し)本格化するのは、その後やっと昭和初期になってからである。
私は大学で山と登山の文化史を専門の美学芸術学の立場から講じている。最近では群馬の山岳史に対しての関心を抱いている。この最初の利根川本流遡行についても、近代アルピニズム・スポーツ登山の単なる前史を成す冒険的登山という枠組に収まり難い側面が気になる。この関東随一の一級河川の水源に関わる当時の行政側の思惑のことではない。むしろ、その点も含め更に、「沢登り」という西洋的でない登山形態、そして赤城山や浅間山と違い群馬でも当時未だ秘境の奥利根という風土、という契機がそこに独自に介在すると思われる。この明治二十七年の山行には、近代以後の群馬そして日本の山と登山の文化史の特異性を巡る一つの示唆がある気がしてならない。(県立女子大学助教授)
ばば・あきら 熊本県出身。東京大学大学院修士課程修了、フランス・カン大学大学院人文研究科博士課程修了(フランス文学博士)。2000年より県立女子大学へ。美学芸術学専攻。現在、同大美学美術史学科助教授。論文に、≪LE SPECTACLE ET LE DEPASSEMENT DE SOI≫(MODERNITE ET PERENNITE DE J.-J. ROUSSEAU, ed. par T. L'Amynot etc., Paris, Honore Champion, 2002に所収)などがある。
朔太郎とポオ
山本常正

1924年の朔太郎(1886-1942) 前橋文学館「萩原朔太郎―抒情の光彩―」より。
大阪から群馬に赴任して五年目に入った。四年前、群馬で最初に行ったのが前橋文学館である。関西にいた頃から、何か気になっていた朔太郎の記念館を訪れたかったからである。彼がアメリカの詩人ポオに深く傾倒し、大きな影響を受けたということを知っていたからである。おそらく、朔太郎はフランスの詩人ボオドレールを介してポオに急接近したのだろう。あれ程までにフランスに憬れていた朔太郎が、二十五歳の頃から四十六歳で亡くなるまで、やはりポオから決定的な影響を受けたボオドレールを通して、ポオ芸術の核心に共感したと考えるのが、自然なようである。
朔太郎には「ポオ、ニイチエ、ドストイエフスキイ」という随想が残されている。この三人の詩人、哲学者、小説家から朔太郎は各々相異した深い感銘を受けている。彼の詩人としての精神形成に、特にこの三者は大きな役割を果たしているのである。ここでは彼のポオ・ヴィジョンを見てみよう。朔太郎は述べている―「僕のやうな人間でも、若し當時の佛蘭西に生まれてゐたら、たしかボードレエル位の仕事をし、彼ほどの詩やエッセイを書いたであらう。すくなくともボードレエルは、僕にとって「及び得る」といふ自信をあたへる。然るにポオに至っては、徹頭徹尾絶望であり、最初から降参する外に仕方がない。ポオは天才の天才だから、勉強しても追ッつかないし、真似をしても真似ができない。これこそ本當の「奇蹟」であり、文學の中でのミステリイだ」。この最後の文の「奇蹟」、「文學の中でのミステリイ」という朔太郎の表現は、ボオドレールに続き、やはりポオに熾烈に傾注したフランス象徴派詩人マラルメの「彼(ポオ)は・・・事実、絶対文学的事件である」という表現と酷似しているのである。
朔太郎の詩人としての揺るぎない自己確信は、右の彼自身の言葉によって充分窺える。ポオに対しては、朔太郎の詩的直観によって、最初からポオという文学における「奇蹟」を認めている。彼はまたポオを「天才といふ言葉が意味するところの、あらゆる狂気じみた神秘の中で、最も内奥的な気味悪しき神秘」と形容している。この朔太郎の形容は、彼がポオの詩文学の核を、彼の詩的直覚で明晰に察知していたことを示している。それは、朔太郎が「僕にとって一つの文學的聖書」と称するポオの短篇「アッシャー家の崩壊」「ライジィア」等は「それを始めて讀んだ時から、魔のやうに頭脳の底にこびりついて、如何にしても僕の詩的幻想から追ひ出せない」と断じていることからも、首肯できるのである。(県立女子大学教授)
やまもと・つねまさ 1943年大阪府生まれ。関西学院大学大学院博士課程修了。アメリカ文学・比較文学専攻。高野山大学を経て、県立女子大へ。著書に『エドガー・ポオ―存在論的ヴィジョン』(英宝社)、訳書に『ポオとヴァレリー―明晰の魔・詩学』(国書刊行会)など。
わらべ歌に探る県民性
神山雄一郎

ボールで遊ぶ子どもたち
群馬の前橋地方で歌われた手まり歌を調べてみた。
一番始めは一宮、
二また日光中禅寺、
三また佐倉の宗五郎、
四また信濃の善光寺、
五つは出雲の大社、
六つは村々鎮守様、
七つは成田の不動様、
八つ八幡の八幡宮、
九つ高野の弘法様、
十で東京二重橋
この歌は、戦前に主に歌われたようだが、戦後はあまり歌われていない。歌詞は「二は日光東照宮」や「十は東京招魂社、あるいは東京泉岳寺」、富山の方では「富山の招魂社」と地方によって多少の違いはあるが、全国的に歌われたようだ。
一匁のイー助さん、
一の字が大好きで一万一千一百石、
一ト一ト一ト豆、
お蔵に納めて二匁に渡した
この歌は、戦後まもなく最もよく歌われたようだ。歌詞は「二匁のニー助さん・・・」と九匁まで続くが、「一ト一ト一ト豆」のところは、正確には「一斗一升一合豆」であったと考えられる。尺貫法からメートル法に変わり簡略化されたのであろう。地方によっては「大好き」が「嫌い」に、「豆」が「マイ(米)」や「マス(枡)」になり、「蔵」が「フダ(札)」」になったりしている。「豆」は小豆を表していると思われ、変化の激しい小豆相場を好む、ギャンブル好きな地方の姿が浮かんでくる。
一リットラー、一トウシュ、一番船の船長さん、おかいんなさい
この歌は「二リットラー、二トウシュ・・・」となって続いていく。この最初の部分の意味は不明であるが、明らかに船の歌であり、海のない群馬県で船に関して歌われたのは、利根川を始め河川が交易に重要な役割を果たしていたからであろう。また、歌詞が他の曲より短いのは、短気な性格の表れであろうか。更に、「かえる(帰る)」を「かいる」と発音しており、かなり地方色の濃い曲と言えそうである。
あんた方どこさ、肥後さ、肥後どこさ・・・
この歌を知っている人は最も多く、歌詞は全国共通のものである。流行った時代は他の曲より遅く、この後、まりつき自体が全国的に行われなくなっている。
J.ホイジンガーはその著「ホモ・ルーデンス」の中で「子供は種族の歴史を遊びの中で学習する」と述べている。群馬の県民性というものがあるとするならば、子供の遊びの中に、そのヒントが隠されているはずである。わらべ歌を歌うとき、子供たちは歌詞の意味などほとんど考えないし、その歌が地方特有のものかなどと考えることはもちろんない。しかし、その伝承課程でその地方独特の表現に変えられ、無理なく子供たちに伝えられていたことは、手まり歌の例を見ても明らかである。
最近では、わらべ歌はほとんど歌われなくなり、子供の遊び全てが全国共通になってきている。子ども達は今どのような形で県民性という歴史を学習しているのであろうか。
それを探し出すのが今後の楽しみである。(県立女子大学教授)
かみやま・ゆういちろう 群馬県前橋市出身。東京教育大学卒。大阪商業大学
専任講師を経て、県立女子大へ。体育学専攻。現在、同大教授。著書に「健康に自信があ
りますか」(上毛新聞社刊)など。
タウトの机
戸澤義夫

タウトの肖像
(町田洋二氏筆 朝雲兒久臣氏『もうひとりのブルーノ・タウト』より)

タウトの机
(朝雲兒久臣氏『帰ってきたブルーノ・タウト』より)
平成十年以来、何よりも子どもたちのために、そしてそれを通して私の住む地域の文化とこころの活性化を目指すために、詩人萩原朔太郎の名に因んで設立された《朔太郎ジュニア・オーケストラ》の活動に携わっているが、この活動にまつわる、日本では「桂離宮の発見者」として知られる世界的な「建築芸術家」でもあるブルーノ・タウトと群馬との関わりの一端について触れたい。
我がジュニア・オケは、ぐんま日独協会の会長をなさっている平形義人さんの御好意で、三年前から、御母堂がお孫さんを育てられた前橋の《母心堂平方志乃記念館》を練習会場として使わせて頂いているが、この三月末、例年のごとく、契約更正のために渋川にある平形邸をお訪ねした折りのことである。
「どうですか」と見せられたものが、漆塗りのしかも足の部分が斜に突き出している、ちょっと風変わりな文机 (写真) であった。一見して実にすっきりした感じがするのでその旨申し上げたと記憶しているが、それがタウトの指示の下に制作されたものであることを告げられた時には、正直、戸惑いを感じた。「タウトって建築家でなかったっけ?」
しかし、私は不明にして知らなかったが、平形氏に紹介され、お贈り頂いた朝雲久兒臣氏の全六八一頁からなる記念碑的な力作『もうひとりのブルーノ・タウト』(上毛新聞社 平成二年) によれば、彼が主として住まいとした高崎の「小林山 (洗心堂) における活動は、工芸のデザイン制作とその実作指導に、ほとんど精力を集中したといってよい」(p.510) とあり、むしろ「日本では建築家としては不遇であった」(p.520) ことが分る。
しかし、それにしても、何でその活動の一端であるこの机が、本業は眼科医でいらっしゃる平形さんのお宅にあるのだろう?
もちろん、お話好きの平形さんのこと、私の当惑を見透かされたように、細々と説明してくださった。
日本でのタウトが心血を注いだ、いわば彼の魂の表れとも言えるこの机と群馬との感動的な「再会」は「水茎もうるわしい墨黒の文字で書かれた」(p.7) と朝雲氏が紹介されている一通の女性の手紙から始まる。その詳しい経緯は、朝雲氏の『帰ってきたブルーノ・タウト』(風土記出版委員会 平成五年) に「タウト・テーブルの発見」として述べられているので、興味の在る方は、先の著作と合わせてお読みになることをお勧めするが、アクロポリスと桂離宮を比較して世界の識者に「大きな衝撃波」を与えた「国際主義的展望」(p.382) を持つタウトが、日本での寂寥を嘆きつつも「だが、小林山の風景は永遠に美しい。」(p.427) と群馬の地を愛してくれたことは、群馬を、そして日本を考える際に、忘れてはならない重要な事実として私たちに残されているのではないだろうか。(県立女子大学教授)
とざわ・よしお 青森県出身。東京大学文学部美学芸術学科卒。同大同学部大学院文学研究科美学芸術学専攻。博士課程中退。同大同学部同学科助手を経て県立女子大学へ。美学及び音楽美学専攻。現在同大教授。著書に『近代日本の成立』(ナカニシヤ出版 平成一七年)『精神と音楽の交響』(音楽之友社 平成九年)『芸術文化のエコロジー』(勁草書房 平成七年) 等。
循環型社会の構築
礒部明彦

「おから入りパン」を焼く学生たち
10年前、昔の研究者仲間と学会発表の夜、居酒屋でお酒を酌み交わした。それが、夏場なら冷奴、冬場なら湯豆腐が必ずだされた。誰からともなく「豆腐はよく食べるが"おから"は最近ほとんど食べてないなぁ・・・」こんなことが「食品廃棄物(我々は未利用食品と呼んでいる)の有効利用方法について」という私の研究テーマになっている理由である。
我が国の廃棄物の量は年々増加し、現在は約4.5億トン/年に上っている。これだけの量を処理するためには今ある廃棄物処理場だけでは十分ではない。廃棄物が年々増加することを考えるといずれは破綻すると思われる。したがって、あらゆる分野において、廃棄物を減らすためにリデュース、リユース、リサイクルを積極的に推し進めていかなければならないと言われている。また、平成7年には国連大学からゼロ・エミッション(廃棄物ゼロ)と言う概念が発せられたこともあって、世の中は、循環型社会を構築するという強い意思の基に大きく動きだした。
国はこれまでの大量生産大量消費型社会を循環型社会へ移行しようとする強い意思の現れであると考えられる。鉄鋼くず、アルミ缶、スチール缶などのようにリサイクルが進んでいる分野もあるが、食品分野のように、未利用食品のリサイクルが依然として進んでいないところもある。
そこで私達の仕事は"おから"の有効利用に関する研究およびリサイクルに関心のある会社と共同による企業化に関する研究が主なものである。
東洋には食品(食材)に対して"一物全体"という思想がある。食品を丸ごと全部食べるという考え方である。大豆の場合は、煮豆として食べたり納豆として食べたりすれば"一物全体"であるが、大豆から豆腐を作って食べ、副生する「おから」を食べないのは一物全体ではない。豆腐と"おから"の両方を食べてはじめて大豆を食べたことになり、"一物全体"となる。"おから"は、タンパク質・脂質・炭水化物・食物繊維・ミネラル等を含み、食物繊維を含まない豆腐より栄養学的にはバランスがとれている。尚、現在"おから"の他にも群馬県の"地産地消"という考え方を実践すべく、コンニャクの精粉を取る時に生じる"飛粉"や柑橘類の搾りかす、米ぬか、ふすまなどの活用方法を研究中である。(県立女子大学教授)
いそべ・あきひこ 前橋市出身。前橋高校卒。71年に東北大大学院薬学専攻修士課程修了。73年に同大農学部の大学院研究生となり、78年に農学博士。同年から2年間、県衛生公害研究所で嘱託勤務。80年の県立女子大開学と同時に助手。93年から同大教授。現在、同大国際コミュニケーション学部教授。01年2月から群馬県大規模小売店舗立地審議会委員を務める。最近の報告書に「未利用食品の有効利用に関する研究」など。
外国人住民との共生
伊藤健人

多文化共生社会における国語教育のあり方研究会「学校に行こう!すべての子どもの未来のために」シンポジウム 多文化共生と学校教育 報告書。2004年3月に県立女子大で行われたシンポジウムの報告書であり、「多文化共生社会」の中心的課題のひとつである子供の学校教育に焦点を当てた政策提言がなされている。
【外国人住民の増加】群馬県内でも外国人住民は増加しており、外国人登録者数は県人口の2.27%を占める。特に大泉町では約15%が外国人住民であり、全国的に見ても著しく高い割合である。
【カルチャーショック】多くのニューカマー(新たに来た外国人住民)にとって新たな環境での生活は困難を伴うものである。環境の変化によって今までの行動・生活様式が揺らぎ、動揺するような心理状態をカルチャーショックと言う。けれども、旅行などで訪れる短期滞在者はこれが楽しみでもある。迎え入れる側も"お客さん扱い"をし、楽しい思い出をとサービスする。しかし長期滞在者や定住者にとっては、カルチャーショックは日本の生活での致命傷になりかねない。受け入れる側も"客さん扱い"するのでは具合が悪い。将来、同等の住民として共に生活して行かなければならないからだ。ニューカマーの抱える問題は自分たちの問題として撥ね返ってくるのだ。
【日本語教育と日本語支援】ニューカマーと接する際に気をつけなければならないのは、日本語能力と知的能力は別ものということである。頭(母語)で考えている高度に知的な内容を日本語で表現できないだけである。そこで専門的な日本語教育が必要となるのだが、これにはある程度時間がかかってしまうため、語彙や文型が乏しい初級では多くの学習者が自らの考えを十分に表現できないストレスを抱えている。そこで必要となるのが日本語支援である。日本語教師によってコントロールされた一方向的なものではなく、同じ住民としての双方向的なコミュニケーションがなされる環境作りである。これは自然に生まれるものではなく、やはり受け入れ側が意識的に作らなければならない。ボランティアに支えられた支援活動である。「多文化共生社会」では、ニューカマーを"お客さん扱い"せずに一住民として扱い、その上で"困ったときはお互い様"という意識を持つことが重要であろう。(県立女子大学専任講師)
いとう・たけと 東京都出身。神田外語大学大学院言語科学研究科修了。言語学博士。明海大学を経て05年県立女子大へ。現在、同大専任講師。専門は日本語教育・言語学。論文に「イメージスキーマに基づく格パターン構文」など。
群馬の赤ちゃん学
毛塚恵美子

おもちゃで遊ぶ赤ちゃん
群馬で赤ちゃん研究を始めて20年近くになる。出会った赤ちゃんの数は数千人に上るだろう。心理学の分野での赤ちゃん研究は1960年代にスタートした。80年代半ばにはブームを迎えている。それは、「未熟で無能な赤ちゃん」から、「有能な赤ちゃん」への赤ちゃん観の転回であった。近年、ふたたび「赤ちゃん学」に熱い視線が寄せられている。それも従来の医学、教育、心理学を超えた、脳科学、工学などの分野からである。2001年、「赤ちゃんを科学する」というコンセプトで「日本赤ちゃん学会」が設立された。霊長類から、ロボット研究者までをも含む学際的な団体である。当然、研究装置は大がかりで、脳磁計や光トポグラフィなどを駆使したハイテク研究が並んでいる。
私たちの研究はといえば、情けないことに、ようやく昨年、観察用のビデオカメラの一部をデジタル化したところである(県立女子大学特定教育・研究費による)。こんなローテク研究ではあるが、誇れることが二つある。一つは、観察途中でドロップアウトする赤ちゃんが非常に少ないこと(当然のことながら、相手が赤ちゃんだから、泣かれて観察を遂行できなくなることが多いのだ)。もう一つは、月齢のかなり早い段階でさまざまな行動を確認していることである。これは、できるだけ日常に近い自然な状況で観察していることと、私の研究上のパートナーである天野幸子さん(女子栄養大学)があやし上手で赤ちゃんの能力を最大限引き出していることによる、と私は考えている。研究の正否を握る鍵は思わぬところにあるものである。
最近、赤ちゃんの脳研究で先端をいくチブラ博士(ロンドン大学)の論文に私たちの研究が引用された。アイディア次第ではローテク研究でも勝負できるかもしれない!70年代、次々と斬新な実験を報告して世界中の研究者をあっといわせたバウアー博士の研究も、その発想のもとは実に単純なことだった。赤ちゃんを垂直姿勢にしたこと(横にすると赤ちゃんは眠ってしまうのだ)と胴を固定したこと(手が自由に動くようになった)だった。
群馬の赤ちゃんのかしこさを世界に紹介したい――目下、奮闘中である。(県立女子大学教授)
けづか・えみこ 東京都出身。お茶の水女子大学卒。同大学大学院人間文化研究科単位取得退学。発達心理学専攻。現在、県立女子大学教授。
子供が抱く幸福感
佐々木尚毅

群馬県エンゼルプラン「ぐんぐんぐんま子育てプラン」の表紙
「こどもの日」を含む連休が過ぎた。
昭和二三年制定の「国民の祝日に関する法律」には、「こどもの日」は「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」日とある。
制定から半世紀が経ち、多くの自治体が子育てするなら「わが市」「わが県」と謳う今、どれほどの子どもたちが、家庭に満足し、なによりも今の自分は幸福だと思っているだろうか。そもそも、子どもたちは、幸福感をどんな時に抱くのだろう。
数年前、仲間たちと全国調査をした。アンケート調査により、家庭教育をめぐる中・高校生とその親の意識を四千八百組の親と子を対象に調べた。興味深かったのは、親とその子どもの意識のズレである。家庭の満足感(幸福感)について尋ねた。親は、わが子は家庭に満足しているハズと答え、その子は満足感は低いと答えるケースが多かった。そのズレが何によるのかというと、満足感の尺度を親と子が違うものの上に置いていたからである。親は買い与える物に。子は親との触れ合いに。
子どもの満足度を左右する最大の因子は、親と一緒に過ごせる時間の長さ、機会の多さである。そして、会話の内容、食事の時の雰囲気など親との「触れ合いの質と内容」によって満足感を大きくしたり、小さくしたりする傾向が見られた。
さらに注目すべきは、親との密度の濃い触れ合いにより、満足感を持っている子どもは、それと連動させる形で、自分は「大切にされている」という感情を大きくしていることである。親に大切にされていると感じている子どもとそうでない子どもの差が、特徴的に出たのは逸脱行動の可能性についてである。飲酒、喫煙ではそれほどの差はなかったが、薬物の使用や売春についての許容度、自らするかもしれない可能性については、「大切にされている」という感情を持てないでいる子どもほど自分がしてしまう可能性を高く判定した。親から大切にされていないと思う子どもは、自らを大切にできない、という訳である。
当たり前といえば、至極当たり前の結果だ。子どもだった頃を思い出せば容易にわかる話である。褒められたらうれしい。叱られたら悲しい。勉強がすべてじゃない。
親だって子どもの頃には、そう思っていたはずである。しかし、今、子育てをしている親のうち、どれだけの人がこの当たり前を当たり前として、子どもを育てているだろう。
わが群馬県も「子どもを育てるなら群馬県」と謳う。それは親が子育てしやすい環境があるということのほかに、親が子どもの幸福とは何かを理解して子育てしている県という意味であってほしいと願う。(県立女子大学助教授)
ささき・なおき 秋田県出身。立教大学大学院文学研究科博士課程後期課程単位取得退学。立教大学文学部助手等を経て、現在、県立女子大学助教授。教育学専攻。共著『総力戦体制と教育-皇国民「錬成」の理念と実践-』(東京大学出版会)など。
郷愁を誘う白井宿
戸所宏之

白井宿のつるべ井戸
白井宿は渋川の北にある江戸時代の街道跡だ。数百年の時の香りが、街道沿いの屋敷や、道の真ん中を流れる水路から立ちのぼる。群馬にながいこと住んでいるくせにこの宿の存在を知ったのはつい最近である。地図も見ずにドライブしていてたまたま迷い込んだのが白井宿だった。まるでタイムスリップしたようななつかしい光景に私は息をのんだ。郷愁が私を襲う。子供のころの思い出だろうか、それとも、前世の記憶か。わけも分らず私はあたりを見回していた。しばらくして私に切ない感情をもたらした主が知れた。井戸だ。若いひとたちは井戸そのものを見たことがないだろうから地中深く掘られた垂直の虚空がどんな不思議を秘めているか想像できないかも知れない。この街道にはいたる所につるべ井戸がある。役目を終えた井戸のほとんどは木枠で封印されているが、ひとつだけはまだ口を開けたままだ。近づいて鉄格子ごしに奥をのぞき込むと、底にたまった井戸水がのぞき込む私を薄暗く映し出した。その瞬間私は自分がもうこの世の人間ではないと感じた。井戸はそういう場所だ。
ちょうどそのころ、自分の劇団の公演台本を書いていた。締切はせまる。構想は浮かばない。決まっているのは「羊歯の森で」という外題だけだ。公演会場に予定している桐生市有鄰館の煉瓦蔵を下見した。井戸の不思議がまた起った。赤くさびた重い扉を開けて中に足を踏み入れたときのことだ。とたんに空気がふっと動いた。壁一面の赤い煉瓦を見て、まっさきに思い出したのがどういうわけか白井宿のあの井戸だった。そうか、この世とあの世は井戸でつながっているのだ。井戸の向うには羊歯の森や灰に埋もれた町があるのだ。そんなことを奇妙だとも思わずに考えていた。そのときからことばがどっとあふれ始めた。
井戸を掘れ、井戸を掘れ
井戸には埋もれた歌がある
井戸を掘れ、井戸を掘れ
掘ればことばが湧いて来る
ひとがなつかしさを感じるのは単に自分ひとりの思い出をたぐり寄せるときだけではないようだ。(県立女子大学教授)
とどころ・ひろゆき 昭和21年8月、前橋市に生まれる。上智大学大学院修士課程修了。英文学専攻。現在、群馬県立女子大学文学部教授。劇団「群読集団 冬泉響」主宰。著書、『はじめてのシェイクスピア』(PHPエディターズグループ)。脚本、「羊歯の森で」「南町紫陽花小路」ほか。
朔太郎とふらんす
井村まなみ

「愛憐詩篇ノオト第八巻」
(前橋文学館所蔵)より
「ふらんすへ行きたしと思へども
ふらんすはあまりに遠し
せめては新しき背広をきて
きままなる旅にいでてみん。」
よく知られる、朔太郎の詩篇「旅上」の冒頭である。ただこの後に続く詩句となると、すぐに思い浮かべられるひとは少ないかもしれない。「ふらんす」はそれほど遠かったのだろうか。
詩篇が発表されたのは大正二年(一九一三年)。文学者にとって渡仏は大変な冒険旅行であった。永井荷風、与謝野寛、島崎藤村らは、体力財力に恵まれた強者たちだ。一ヶ月以上に及ぶ船旅の末、フランスの地を踏んでいる。朔太郎はと言えば、「日本を離れたい」胸中を明かすものの、両親の反対にあって、計画を放棄。代わって彼が選ぶのは、汽車旅行である。詩篇は次のように続く。
「汽車が山道をゆくとき
みづいろの窓によりかかりて
われひとりうれしきことをおもはむ」
新橋―横浜間に鉄道が開通したのは一八七二年。日本の鉄道敷設が本格化するのは八〇、九〇年代である。生糸の集散地であった前橋に線路が届くのは一八八四年。朔太郎誕生は一八八六年だから、彼は鉄道網の発達とともに成長していったと言えよう。時刻表を眺めると、前橋―上野間はそれなりの時間を要する列車旅行であったようだ。運賃も馬鹿にはできない。旅人は新調した背広に身を包み、颯爽と列車に乗り込む。この旅を、フランス行きの代わりにしようと考えたのである。
当時はまた、フランス詩の翻訳が始まった時代でもある。遠い異国に憧れる朔太郎の思いは、上田敏の『海潮音』(一九〇五年)、永井荷風の『珊瑚集』(一九一三年)を通じて、フランス文学の受容という形に変じる。なかでも彼は、ボードレールに深い関心を抱いた。優柔不断の連続のような人生、女性を歌った詩篇が発禁処分を受けるなど、国と時代を越えて、ふたりの詩人には共通点が見受けられる。社会生活を営むことに多大な困難を覚えたふたり。引き換えに彼らが見つめ続けたのは、言語の深淵であった。言葉の革新に大きな役割を果たした詩人として、それぞれの国でやがて揺るぎない地位を獲得する。
「五月の朝のしののめ
うら若草のもえいづる心まかせに。」
創作ノートで「五月」と題されていた詩篇「旅上」は、この二行で終わる。若い詩人の弾む思い、眼前に広がる未知の可能性が余すところなく伝わってくる。前橋文学館が、朔太郎の紹介ビデオの冒頭に用いるのもやはりこの詩篇だ。スクリーンに大写しされる直筆原稿は、新緑に包まれた山あいの風景、そこを走り抜ける機関車の映像とともに、前橋をフランスへと結ぶ遥かな旅に、わたしたちを誘い続ける。(県立女子大学助教授)
いむら・まなみ 東京都出身。神戸大学文学部卒。パリ第八大学にて文学博士号取得。専門は十九世紀フランス詩。一九九九年より県立女子大(助教授)。著書に「アルチュール・ランボーの『後期韻文詩』に於ける否定の詩学」。
暮らしと密接な地名
北川和秀

群馬学連続シンポジウム第4回「群馬の地名」のポスター
高崎市山名町に山ノ上碑という古碑があり、天武天皇十年(六八一)の成立と考えられる。古碑といえば、上毛かるたに「昔を語る多胡の古碑」とよまれる多胡碑が有名であるが、山ノ上碑は多胡碑よりも三十年古い。この銘文中に「佐野」という地名、「新川臣(にひかはのおみ)」「大児臣(おほごのおみ)」という人名が見える。「佐野」は現在の高崎市上佐野町・下佐野町付近に比定され、「新川臣」は勢多郡新里村の新川、「大児臣」は前橋市大胡町と関係する可能性がある。もしそうだとすれば、当時の地域交流の範囲が意外に広かったことが伺え、興味深い。このような推測ができるのも、佐野、新川、大胡などの地名が現存しているからであり、地名のもつ価値はまことに大きいと言える。
こういった古代の歴史に関わるものだけでなく、地名には、自然地形に由来するもの、天候気象に由来するもの、人間活動に由来するもの、などなど様々なものがある。そして、それらの地名は、程度の差こそあれ、いずれも人々の暮らしと密接に関わっている。我々はそれらの地名を通して、人々の暮らし、歴史、ものの考え方、ことばのありさまなどをうかがい知ることができる。まさに、地名は形のない文化財であると言えよう。
群馬県立女子大学では「群馬学」の確立をめざして、昨年度から群馬学連続シンポジウムを開催している。本年度の第一回(通算第四回)は「群馬の地名」というテーマで五月十四日(土)に実施する。内容は、谷川健一氏(日本地名研究所所長)の基調講演「地名の喚起力」。引き続き「地名から群馬を考える」というテーマでのシンポジウムで、パネリストは、上野智子氏(高知大学教授)、鏡味明克氏(愛知学院大学教授)、澤口宏氏(群馬地名研究会会長)の三氏である。午後一時二十分開始。会場は本学講堂。地名に関心をお持ちの方々が多数ご来場くださるよう、心からお待ち申し上げる。(県立女子大教授)
きたがわ・かずひで 東京都出身。学習院大卒。同大学院人文科学研究科修了。学習院大助手を経て、県立女子大へ。国語学・国文学専攻。現在、同大教授。著書に「群馬の万葉歌」など。
優しく描かれた花
高橋綾

『愛、深き淵より 星野富弘』(左)と 筆者のデザインによるパンフレットの表紙(右)
私の出身大学の入試には、デッサン、立体構成、色彩構成の3つの実技試験がある。私はデッサンと立体構成には自信があったのだが、色彩構成で出題される「花」がどうしてもうまく描けなかった。私の描く花は、アルミや鉄などの固い素材で出来た花のようになってしまうのだ。「自分は自然物が好きではない。むしろ工業製品の方が美しい」などと、出来ないことを「嫌い」と言ってごまかし、その結果二年間浪人しても「花」は「花」にならなかった。そして、三浪目の冬。うまく描けない花の資料を探すため図書館へと足を運んだ。花の写真集や日本画家の作品集を閲覧するのだが、どれもピンとこない。そのとき、決して上手ではないのだが、とても優しく描かれた花に目が止まった。
『愛、深き淵より 星野富弘』
中学校の体育教諭の筆者が、授業中、頸椎を損傷し手足の自由を失ってしまう。その後、口に筆を加えて絵や文字を描く美術作家となるまでの自伝日記集の表紙だった。その本の中で筆者は、初めて花を描いたときのことを次の様に話している。『力なく下を向いていた。元気だったときのように上を向かせて描いてやろうと思ったが思い直して下向きのまま描いた。―中略―ある日新聞でハルジオンのことが載っているのをみつけた。「蕾は下向きにつく」と書いてあった。私はありのままに描いてよかったと思った。偉大な自然がつくったものを、私のような小さな者が手を加えようとしたことを、恥ずかしいと思った。』と。この言葉を意識した私は、その年大学生となり、現在、筆者と同じ群馬県の教員として働いている。
今私は、群馬学に関するポスターやパンフレットのデザインを担当させて頂いている。星野氏が語っていた「ありのままに描いて」を意識しながら、群馬という自然多き町を表現できればと思っている。ありのままの群馬について考えてもらうきっかけとなることができれば幸いである。(県立女子大学助教授)
たかはし・りょう 神奈川県出身。東京芸術大学デザイン科卒業。同大学大学院美術研究科修士課程デザイン修了。同大学非常勤講師、株式会社富士通ゼネラル(デザイン部)を経て、2002年県立女子大へ。現在、美学美術史学科デザイン専任講師。同大学の広報に関わるグラフィックデザイン全般を担当。遊具、動く造形などのデザイン、研究を専門としている。2005年度、美ヶ原高原美術館ミュージアムショップにてあかりや動きを用いた遊具作品を販売予定。
文学の中の上毛三山
権田和士

土屋文明記念文学館編『群馬の作家たち』(塙書房 一九九八年刊)。群馬に縁ある作家たちに関する詳細なデータが記されている。
群馬県立女子大学のある玉村町からは、赤城・榛名・妙義のそれぞれに美しい姿を見ることができる。群馬県民は、おのおのの思い出とともに格別の思いをそれらの山に抱いているであろうが、上毛三山は県外の人たちにもよく知られている名山であり、文豪たちも、その人にいかにもふさわしいと感じられる山を訪れ、優れた文学作品を残している。
赤城を描いた小説には、白樺派の代表的な作家志賀直哉の「焚火」(一九二〇年)がある。山の自然とそこに住む人々との交流を鮮やかに描き出したこの作品は、志賀の代表作の一つであるだけでなく、日本の近代文学にとっても重要な意味を持つ心境小説の傑作である。小説末尾の、焚き火を湖水に抛るシーンは実にうつくしい。
榛名には、川端康成とともに新感覚派のリーダーであった横光利一の佳品「榛名」(一九三五年)がある。人生に疲れた主人公がひとときの休息を榛名湖畔で過ごす様子を描いた小説で、静謐な印象を受けるが、「私は立ち上つて湖の底を覗いてみた。しかし、いつまでたつても、私はただ大きな私の影が湖面の上に倒れかかつて、右から照り輝いてゐる満月の光と争つてゐるのを見ただけである。そのとき、一疋の蟋蟀がはつと満月の中から飛び込んで来たかと思ふと、冷たく私の右側の鼻柱を蹴りつけて見えなくなつた。」というような新感覚派らしい表現は、静かさの中に潜む激しさを鋭く浮かび上がらせている。
妙義には、夏目漱石の親友であり、近代俳句の創始者である正岡子規が大学の遠足で妙義登山を行った際の紀行文「第六回文科大学遠足会の記」(一八九二年)がある。子規は大学生たちの珍道中をおもしろおかしく描写しながら、多くの俳句を記している。その中から三句。
石門に雲の宿かる紅葉かな
榛名春赤城夏妙義を秋の姿哉
行く秋をさらに妙義の山巡り
(県立女子大学助教授)
ごんだ・かずひと 群馬県出身。東京大大学院人文科学研究科修了。恵泉女学園大学を経て、県立女子大へ。日本近代文学専攻。現在同大助教授。論文に「小林秀雄の再検討」など。
江戸と上毛の文化交流
榊原悟

「特別展示 戸方庵井上コレクションを愉しむ―群馬県立女子大学芸術学研究室による8つの視点」図録
一昨年(平成十五年)十一月十五日から十二月十四日まで県立近代美術館で「特別展示 戸方庵井上コレクションを愉しむ―群馬県立女子大学芸術学研究室による8つの視点」が開催された。
室町時代の水墨画(すいぼくが)をはじめ琳派(りんぱ)や文人画(ぶんじんが)、禅林(ぜんりん)美術などの作品で名高い井上コレクションの素晴しさについては、改めて言うまでもあるまい。内容といい点数といい、公立美術館の古美術コレクションとして日本有数のものだ。
そのコレクションの全容を十二年ぶりに公開するに当って、単なる名品の羅列に終わらせたくない県立美術館側の要請を受け、改めて作品を検討した結果、展示に次の八つの柱を設けることにした。
- 筆のたわむれ―井上コレクションの水墨画
- 宗達の見た仙人―琳派のイメージ継承
- 隅田川に遊ぶ
- 朝顔の交わり
- 團十郎の見た團十郎
- 珍鳥渡来記
- 水中をのぞく
- 井上コレクションを裸にする―贋作も見てみよう
これによって展示内容にアクセントが付けられたはずだ。それとともに、各作品の新たな価値と魅力も見出されたに違いない。
ところでこの展覧会の企画を通じて重要なことに一つ気がついた。それはコレクションの創始者井上房一郎氏がどれほど意識して収集したか否かは別にしても、結果的に、このコレクションに江戸の文化・文政期以降の画家・文人たちの作品が少なからず含まれているという点である。酒井抱一(さかいほういつ)や谷文晁(たにぶんちょう)、亀田鵬斎(かめだぼうさい)らのものがそれで、先の展覧会の柱の3、4に分類した。
興味深いのは、彼らがまた『惜花帖(せきかじょう)』と名付けられた書画帖に作品を寄せている点だ。これは桐生の豪商佐羽淡斎(さばたんさい)(一七七二~一八二五)が、亡き兄の追悼のために編んだもので、まさしく当時の江戸と上毛(群馬)との盛んな文化交流を物語る。井上コレクションにはその彼らの魅力的な小品も含まれていたのだ。しかも桐生の浄運寺には抱一や文晁の大作も残されていると聞く。それらを一堂に展示すれば、江戸時代の群馬の、江戸との交流や上毛の熱い文雅愛好の風を具体的に示すことができるに違いない。わたしは現在(いま)そんな展覧会の実現を夢想しているのだが......。(県立女子大学教授)
さかきばら・さとる 愛知県出身。早稲田大卒。同大学院文学研究科修了。サントリー美術館主席学芸員を経て、平成九年県立女子大教授。文学博士。日本美術史専攻。著書に「日本絵画の見方」「江戸の絵を愉しむ」「日本絵画のあそび」「美の架け橋―異国に遣わされた屏風たち」などがある。
「グローカル」の流布
片桐庸夫

県立女子大国際コミュニケーション学部のパンフレット
「地域的特性も考慮に入れながら地球的視野に立った」という意味の言葉「グローカル」を耳にするようになった。どうも「グローバル」と「ローカル」の合成語のようである。
「グローカル」の流布は、米ソ冷戦が終了し、グローバル化がますます進捗する今日の国際情勢において、地域・国・世界という文脈の中で諸事象を理解する必要があるとの観点から、地域研究・地域理解が不可欠であると改めて認識されたことをも示している。
理由は、主に次の六点にある。(1)冷戦終了後のソ連崩壊の結果、「帝国論」への関心の高まりに示されるように、アメリカが好むと好まざるとにかかわらず世界的規模で影響力を持つ唯一の超大国となったこと。(2)そのアメリカを核とする多国籍軍が冷戦終了後初の低強度紛争である湾岸戦争においてイラク軍を破って以来、アメリカとイスラム世界との確執が従来以上に深刻化したこと。(4)その延長線上に位置付けられる九・一一事件を契機として、世界が国際テロリズムとの戦いの時代に移行したこと。(5)世界のアメリカ化と等しいと受け止められたグローバリズムと地域主義の対立緩和、異文化共生の問題が世界的課題として浮上したこと。(6)以上の反省に基づいて、グローバル化時代においては自国にしろ他国にしろ地域レベルの理解がまずもって必要との認識が生まれたこと。
以上、世界の動向の一端を概観しただけでも、県立女子大学文学部を中心に開始された群馬学確立に向けての取組み、実践的な英語運用能力を身につけ、地域・国・世界という文脈の中で問題の理解・解決を志向する国際的人材の育成を目指す国際コミュニケーション学部の新設は、ともに世界史的かつグローバルな要請に適っているといえよう。
更には、今後両学部の協力によって、より多面的で発想豊かな群馬学の構築も可能となり、地域研究の核としての県立女子大学の存在意義も一層高まることが期待される。(県立女子大学教授)
かたぎり・のぶお 新町生まれ。慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程単位取得満期退学。現在県立女子大学国際コミュニケーション学部教授・法学博士。専攻は政治学・国際関係論・外交史。著書に『太平洋問題調査会の研究』など。
世界で活躍、深井英五
稲野強

明治29年、イスタンブールにて。深井英五(左)、徳富蘇峰(右)
ここ数年来、一人のハンガリー人の足跡を追っている。この男の名は、ヴァームベーリ・アールミン(1832頃―1913)。1862年、彼はハンガリー語の起源を求めて、大胆にもイスラムの托鉢僧に変装して、メッカから故郷に戻る巡礼の群れに紛れ込み、鎖国状態の中央アジアのイスラム汗国に潜入した。疑り深いハーンの謁見に耐え、命拾いしたのは、学問的情熱とコーランをアラビア語やトルコ語で念誦でき、14ヶ国語を操れる抜群の語学力のおかげ。こんな男の冒険話を当時のヨーロッパは放っておくはずがなかった。
帰欧後、彼は一躍時代の寵児になった。まず言論界が騒ぎ、さらにイギリス女王、フランス皇帝までもが競って彼を宮殿に招き入れ、これに負けじとオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世は彼に大学教授のポストを用意した。浮かれ騒ぐ杜交界を尻目にあくまでも冷静に彼の語学力と豊富な情報を利用したのは、当時中央アジアでロシアと覇権を争うイギリス外務省と諜報機関。彼らは彼を厚遇し、すっかり反露・親英家に染め上げた。
この男に会った最初の日本人こそ群馬きっての国際人、高崎・柳川町生まれの深井英五(1871―1945)である。彼は、出世して日銀総裁にまで登りつめた。彼の一生を支えたのは、米国人も驚くほど卓越した英語力。英語を学びたい一心の深井少年が叩いた門は語学学校ならぬ西群馬教会、ついで同志杜である。そこで徳富蘇峰との運命的な出会いがあった。現実家の蘇峰は思索型の「悩める若者」深井の面倒を実によく見た。24歳の深井を通訳・書生風に仕立て、1896年(明治29年)春に世界漫遊に連れ出したのもその表れである。
さて深井と蘇峰は、ロシアでトルストイを訪問した後、トルコ経由でハンガリーのブダペストに入り、そこでヴァームベーリに会った。彼らは眼下にドナウ川を見るブダの高台で歓談した。日清戦争後日本人に漲る反露感情は、ヴァームベーリの共感を呼んだ。その後深井が日露戦争時に高橋是清の懐刀として外債募集で欧米を回ったのは周知の通り。一方ヴァームベーリも日露戦争時にウィーンの日本公使牧野伸顕の依頼で反露宣伝活動に努めた。明治天皇はヴァームベーリに勲2等瑞宝章を与え、その功績に報いたのである。
英語力を駆使して国際ビジネス界で活躍した深井の生き方は、「群馬から世界へ」を合言葉にする、我が新学部の教育方針とぴったりと符合している。(県立女子大学教授)
いねの・つよし 東京都出身。上智大卒。早稲田大大学院文学研究科博士課程修了。西洋史専攻。専門はハプスブルク帝国の民族問題。現在、県立女子大学国際コミュニケーション学部長。共著に『ドナウ・ヨーロッパ史』(山川出版社)など。
田舎の柏木義圓
市川 浩史

柏木義圓
日露戦争時の海軍軍人秋山真之や文学者正岡子規らの交流や人間模様を描いている司馬遼太郎の『坂の上の雲』は人口に膾炙しており、たいへんおもしろい小説で私も愛読している。しかし、特定の人を詳細に描こうとした余りか、どこか戦争というものを対岸の火事視して、戦争そのものの是非などは詮議の外であるようにみえる。
日露戦争において大日本帝国の軍隊は中国東北部を主な戦場としてロシアと戦ったのだが、国内にあってこの戦争を不義の戦いとして堂々と反対を表明した少数の覚めた人々がいた。そのうちに内村鑑三や柏木義圓らキリスト者がいた。高崎藩士の家に生まれた内村は無教会派キリスト教の創始者として知られ、<御真影>不敬事件の当事者であった。彼の思想的影響は国内はおろか朝鮮半島にまで及んだが、柏木は群馬県内でさえもそれほどよく知られているとはいえない。
柏木義圓は明治三十年から昭和十年までおよそ四十年に亙って、父祖の地・安中の組合キリスト教会に牧師として仕えた。旧安中藩士であった柏木家の先祖隼人が上州に来た本願寺法主に接して出家して寺を創設したことから柏木の生家柏木山西光寺が始まっている。その柏木が明治三十年に父祖の地に建てられた安中組合教会に牧師として招聘された。
柏木は安中に赴任した翌年から上毛地方の諸教会の伝道誌として『上毛教界月報』を創刊し、その事実上の主宰者として毎月の巻頭に自ら論陣を張った。日露戦争非戦論はその巻頭論文において表明された。つまり東京という日本の中央ではなく、群馬県の安中という<田舎>から表明されたのである。じつは柏木には都会の大教会への赴任の話も何度かあったのだが、全部それらを断って生涯主体的に安中に在った。東京の内村に対する安中の柏木。柏木のこの<田舎>性はもっと知られ、そして評価されるべきだ。(群馬県立女子大学教授)
いちかわ・ひろふみ 東北大大学院文学研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)。現在、県立女子大学教授。日本思想史学専攻。著書に「日本中世の歴史意識-三国・末法・日本-」(法藏館)など。
身近な事跡語る漢文碑
濱口富士雄

豆腐来由碑(群馬町観音寺境内)
群馬学は、広範囲な視野から群馬の来し方行く末を分析してゆくことによって始めて豊かな成果が期待される。その一つの視点として漢文碑の存在がある。群馬では、七・八世紀の上野三碑が古代群馬の豪族のようすや仏教の普及を知るうえで貴重な史料となっていることは論を待たないが、実は江戸時代の安永の頃から、明治・大正にかけてもかなりの漢文碑が建てられ、文書史料のすき間を補ううえで一定程度の役割を果たしている。ただ記述が漢文であるという取っつきにくさはあるものの、ほとんどの碑石が常に見やすい状態で身近な事跡を語りつつ存在している。
太田市にある子育て呑龍で知られる大光院境内の「上野大光院故信講碑」には、徳川家康の発言として上野の人々の気質に対する評が記されている。大光院を徳川の祖に当たる新田氏ゆかりの寺社として再興するために呑龍上人を選任したいきさつとして「家康は人に、上野の習俗は片意地を張って屈しないこと(強梗)をたっとぶので、その民衆を帰依させるには、豪傑の人材でなければ無理であろう、と語った。そこで上人を選んだ」とある。家康においてすでに、群馬の県民性として「強梗」が認識されていたのである。
また、群馬町の観音寺境内にある「豆腐来由碑」は感動的な碑石の一つである。豆腐製造で財をなした業者が、豆腐の創製者に報いるべく、豆腐の来歴の調査をふまえた上で建てたものである。そして中国の漢代の淮南王劉安と文禄の役の折に朝鮮からわが国へ製法を持ち帰った岡部治部右衛門とをたたえている。これは、わずか八十年ほど前の碑ではあるが、群馬の企業人における、自らの職種に対する誇りの高さとその職種の創始者に対する感謝の思いをゆるがせにしない生真面目な職業倫理の高さとを証す遺物ともなっていくことであろう。(群馬県立女子大学教授)
はまぐち・ふじお 東京都出身。大東文化大卒。東京教育大大学院修士課程、大東文化大学大学院博士課程。博士(文学・筑波大学)。秋田大学助教授を経て、県立女子大学へ。中国古典学専攻。現在、同大教授。著書に「清代考拠学の思想史的研究」など。
新聞はハレの舞台
市川祥子

上毛新聞〈日曜文芸〉における伊藤信吉の詩
大正十二年(一九二三)春、小柄で神経質そうな青年が一人、人目を気にしながら上毛新聞の社屋に近づいた。手には〈日曜文芸〉宛の封筒。萩原朔太郎の『月に吠える』に感動して詩人を志した青年は、郵便受に自作の詩を投げ入れたのである。何度目の投稿だったのだろう、詩は紙面を飾り、彼はこのページの常連となった。次のように回想している。
大正十二、十三、十四年と、三年のあいだ私の投書はつづいた。年齢的には十七歳から十九歳である。掲載された作品は、いま読むといかにも稚拙だが、それらの幼い作品が私の文学的出発点だった。その時の私は同人雑誌の仲間もなく、上毛新聞を一つのよりどころにして、のろい足どりで自分の文学をそだてていた。
(「上毛新聞の思い出」、昭五二・十一・一)
青年の名は伊藤信吉。昭和に入ってアナキスト詩人として認められ、続いてプロレタリア詩人として大活躍するのはご存じの通り。この時期は群馬県庁に勤めていた。
上毛新聞〈日曜文芸〉のページは大正十年(一九二一)八月に始まり、原稿募集記事に「日曜文芸に採用の創作、詩歌は主として毎日集まつて来る投書の中から特に優秀なるものを選抜して掲載し、意義あるものを作りたいと思ふ」とあるように、読者からの投稿に大きく紙面を割いたことを特徴とする。新聞はハレの舞台。伊藤のような青年にとって、自分の詩が地元で有名な文学者と肩を並べているのが、いかに誇らしかったことか。この喜びと自負とが、無名の新人の、不安で困難な詩人への道のりを支えたことは想像に難くない。
他にも〈日曜文芸〉を心の支えに活動を続けた文学者は多いはずだが、その調査は始まったばかり。幸いにも過去の上毛新聞は散逸をまぬがれマイクロフィルムで閲覧できる。紙面から、かつてこの地で生きた人々の躍動をくみ取るのは現代の我々の仕事である。(群馬県立女子大学専任講師)
いちかわ・しょうこ 愛知県出身。早稲田大大学院文学研究科修士課程修了。現在、県立女子大助手。近代日本文学専攻。専門は泉鏡花。近年、群馬県出身の作家にも研究対象を広げている。
武男と浪子の名場面
杉本優

徳富蘆花『不如帰』
「いかばかり人妻は身にひきつめて嘆くらむ/まだ山科は過ぎずや/空気まくらの口金をゆるめて/そつと息をぬいてみる女ごゝろ/ふと二人悲しきに身をすりよせ/しのゝめ近き汽車の窓より外を眺むれば/ところもしらぬ山里に/さも白くさきて居たるをだまきの花 」(傍線引用者)。「みちゆき」(「夜汽車」)の後半である。一九一三年五月、白秋主宰の雑誌『朱欒』(ざんぼあ)に掲載された。「旅上」らと共に詩壇への登場を告げた詩である。
はじめの傍線部について、月村麗子氏の研究などでわかったことがある。徳富蘆花の小説『不如帰』下篇にある、旧山科駅での武男と浪子の有名なすれ違い場面を踏まえているのである。一方に、新派の舞台や活動写真、のぞきからくりなどでの広範な『不如帰』受容があり、その名場面の一つにこの山科駅すれ違いがある。他方、朔太郎の当時の書簡に『不如帰』の読書体験が確認できる。朔太郎は前年夏発覚した北原白秋と人妻松下俊子との、いわゆる桐の花事件に関心を寄せ、自分自身も人妻エレナとの関わりを重要なモメントとして、この四月自筆歌集『ソライロノハナ』を編んだ。「割かれた愛のシンボル」(月村氏)としての「山科」がうたい込まれたゆえんである。後の傍線部については、一九一二年五月帝国劇場で上演された、シェイクスピア『ハムレット』(坪内逍遙訳)第四幕第五場でのオフィーリアのせりふを論拠として、「をだまき」に不義・姦通の象徴を読む勝田和學氏の研究がある。「割かれた愛」は二人の「みちゆき」に換骨奪胎され、朔太郎詩が立ち上がる。
テクストの細部に宿るものを読み解いていくと、他のテクストとの思いがけない出会いがあり〈交通〉がある。人物レベルではこの詩の掲載を契機に室生犀星との交流が始まり、翌一九一四年には山村暮鳥を加えた三人で人魚詩社を結成する。尾山篤二郎、高橋元吉、大手拓次らとの交流も見逃せない。しかし〈交通〉としてテクストをとらえ、人物をとらえるとき、群馬は一旦括弧にくくっておかなくてはならない。髭の男(広田先生)は三四郎に向かって言う。「熊本より東京は広い。東京より日本は広い。」「日本より頭の中の方が広いでしょう」(夏目漱石『三四郎』)。「贔屓の引倒し」になることなく、囚われない精神で、細部に宿るものからテクストの〈交通〉を考えていきたいものである。(群馬県立女子大学教授)
すぎもと・まさる 高知県出身。東京大卒。同大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。武庫川女子大、奈良教育大を経て、県立女子大学へ。国文学専攻。現在、同大教授。共著書に「詩う作家たち」(至文堂)など。
春の句集「せりのね」
安保 博史

玉村八幡宮境内の芭蕉句碑「十六夜塚」。「やすやすと出でていざよふ月の雲」。芭蕉句碑は群馬県内に220基(全国第2位)あり、上州俳壇の隆盛がしのばれる。
江戸期の俳書に収められた作品やその作者の顔ぶれを眺めていると、いかに日本人が江戸の昔から、老若男女、身分の上下も問わず、「俳句」という世界一コンパクトな〈感動記録装置〉に親しみ、その小さなことばの器に日々の興趣を盛り、文雅を楽しんでいたかが実感できる。そして、「俳句」を仲立ちとして、見たこともない遙かな過去の人と対話し、詠み込まれた詩的世界を共有し合って、わくわくするほどの興奮と、何とも言えない感慨を抱くことがある。まさに「ひとり灯(ともしび)のもとに文(ふみ)をひろげて、見ぬ世の人を友とする」(『徒然草』第十三段)醍醐味である。
私がいま最も魅了されているのは、大坂の人で行脚の末に上州上蓮沼(伊勢崎市)に移住した栗庵似鳩(りつあんじきゅう)が編んだ『せりのね』(安永八年[一七七九]刊)という春興集だ。春の句ばかりを集めた本書は、概して「平明」「実景実感」的な作風を志向しているが、
軒端や春の日うけに干温(う)どん 倚流
行はるや名も無き草の小一尺 利川
いろいろの草見覚へむはるの暮 其室
といった、上州の人々が「名も無き草」や農村の日常生活に春の詩美を発見した佳句(かく)などからは、上州俳壇の豊かな文学的土壌と、上州の自然をいとおしむように観賞する人々の瑞々(みずみず)しい精神が窺える。読み進むうちに、ああ、もっと私も上州の自然を愛そう、春になったら野に出て、「いろいろの草見覚へむ」という気になってしまう。『せりのね』は講談社『蕪村全集』第八巻に活字化されている。ぜひ読んでみていただきたいと思う。(群馬県立女子大学教授)
あぼう・ひろし 愛媛県出身。中央大大学院博士課程単位取得退学。九州大谷短大助教授を経て、県立女子大学へ。現在、同大教授。近世俳諧・和漢比較文学専攻。主論文に「貞享初年の新風」「龍草廬と陶淵明」「蕪村と漢文学」など。
「鉢木」の舞台 佐野
石川泰水

常世神社
群馬の地を舞台とする古典文学作品でもっとも有名なものの一つが、謡曲「鉢木」である。大雪の夜、旅僧に身をやつした最明寺入道北条時頼が、上野国佐野で佐野源左衛門常世のもとに宿を求め、常世は秘蔵の鉢の木をたいて暖をとらせ、後に鎌倉からの召集に真っ先に駆けつけた時に、一夜のもてなしへの返礼として、時頼から梅・桜・松の名を持つ三つの土地を賜った、という話である。話に聞き覚えがあっても、舞台が群馬県内であることを知らない人も多いかもしれない。佐野の地の所在を言い当てられる人は、むしろ少数だろう。高崎市内、上佐野町・下佐野町・佐野窪町といった町名にかろうじて名を残す烏川の東岸の地であり、この話にちなんだ常世神社という小さな神社が建てられている。
ところで主人公である佐野源左衛門常世は実在人物ではなく、また特定のモデルがいたわけでもないらしい。だとすれば自然と一つの疑問がわいてくるだろう。群馬県民にさえ馴染み深いわけでもないこの佐野が、なぜ「鉢木」の舞台とされたのだろうか、と。
実は佐野は上毛三碑の碑文に見える古い地名で、『万葉集』上野国東歌の中にも多く登場する。そこに見える「佐野の舟橋」は『枕草子』の「橋は」の段に取り上げられ、また平安時代以来和歌に多く詠まれた、群馬を代表する歌枕(和歌に登場する地名)であった。『新古今集』の代表的な歌人藤原定家の名を冠した定家神社がここにあるのも、そんな関係だろう。そして「鉢木」同様、佐野を舞台とする謡曲「舟橋」というものも存在する。
佐野は、古典文学の世界において群馬でもっとも名高い地であった、と考えて良かろう。それで疑問のすべてが解決されるわけではないが、まずは前提として、佐野という地の意義を再認識することが重要であると思うのである。(群馬県立女子大学教授)
いしかわ・やすみ 埼玉県出身。東京大卒。同大学院人文科学研究科単位取得退学。昭和61年に県立女子大学に赴任し、現在、同大教授。日本文学専攻、とくに中世和歌の研究を専門とする。著書に和歌文学大系23「式子内親王集・俊成卿女集・建礼門院右京大夫集・艶詞」(共著)。
源氏物語「上野の親王」
竹内正彦

源氏物語などの王朝物語とその絵巻
源氏物語に登場する人物は四百三十余名ともいわれる。そこには光源氏や薫、紫の上や浮舟といった男女両主人公はもちろんのことながら、わずか一度しか登場しない人物も含まれる。源氏物語の魅力のひとつは、これらの人物たちひとりひとりが生き生きと描き分けられ、実に緻密な物語の世界が創り上げられていることにあろう。
「宿木」巻に見える「上野の親王」も源氏物語にたった一度だけ登場する人物である。女二の宮と碁を打つ今上帝が人を召して殿上に誰が伺候しているかとお尋ねになった折、「中務の親王、上野の親王、中納言源朝臣さぶらふ」と奏上されるが、このことばのなかの「上野の親王」がそれである。「中務の親王」は今上帝の親王とされる人物で、「中納言源朝臣」は薫のことをさすが、もうひとりの「上野の親王」は、古来、系図などが不明の人物とされている。平安時代の上野国は、上総、常陸とともに、親王がその国の守(太守)に任じられた親王任国で、親王自身は任地には赴くことはなかった。この「上野の親王」にも上野国にやってくることのなかったそうした親王たちの姿を思い浮かべてよいだろうが、それにしてもなぜここで「上野の親王」なのか。
源氏物語の「上野の親王」はこの箇所にしか描かれないが、うつほ物語における「上野の宮」は、身辺に「陰陽師、巫(かんなぎ)、博打(ばくち)、京童、媼、翁」などを集め、あて宮という姫宮の入手を画策するといった異彩を放つ人物として描かれている。うつほ物語の「上野の宮」と源氏物語のそれを安易に結びつけることはひかえねばならないが、歴史上の「上野の親王」や「上野の宮」たちをも視野に入れつつ源氏物語の「上野の親王」の持つ意義は考えられてよいだろう。王朝物語という虚構の世界であるからこそ、そこには平安京の貴族たちが抱いていた上野国のイメージが浮かびあがってくるかもしれない。千年もの昔の、しかも遠く離れた都で書かれた王朝物語の世界にも〈群馬〉を見つめ直す視座がひそんでいるように思われるのである。(群馬県立女子大学助教授)
たけうち・まさひこ 長野県出身。国学院大卒。同大学院文学研究科博士課程後期単位取得退学。現在、県立女子大学助教授。日本文学、とくに源氏物語を主とした中古文学専攻。共編著に「源氏物語事典」(大和書房)など。
地名は文化財、念頭に
北川和秀
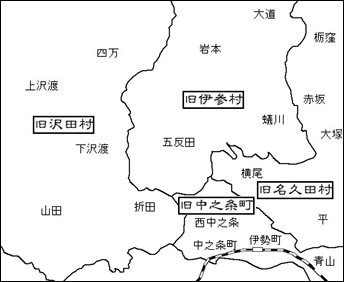
中之条旧村図
昭和三十年まで吾妻郡に伊参(いさま)村という村があった。この年、伊参村を含む一町三村が合併して現・中之条町が成立したときに、この村名は消滅したが、「伊参」という地名は今も「伊参幼稚園」「伊参スタジオ」などという形で残っている。
この地名は古く、平安前期の百科事典『和名抄』に、吾妻郡内の郷名として「伊参」が見え、「伊佐萬(いさま)」と読ませている。「さま」を表記するのに「参」の字を用いるのは、奈良・平安時代特有の古風な表記で、同じく『和名抄』には利根郡内の郷名として、「なましな」を「男信」と表記した例があり、これも同種のものと言える。
「伊参」という特異な表記・読みの地名が、千年以上にもわたって存続していたことは、大きな驚きであり、まさに「地名は文化財である」という好例のように思える。
ところが、実は、伊参村の名は、明治二十二年に原岩本・五反田・蟻川・大道新田という四ヶ村が合併して新しい村ができた時に付けられた名であって、千年にわたって連綿と続いてきた地名というわけではないのである。新しい村の名を、なぜ伊参村としたのか。それは、そのあたりが古代の伊参郷に属していたという伝承によるということである。
新地名を決めるに際して、古代の由緒ある地名を復活させようという姿勢は大いに評価できる。しかし、古代の伊参郷の範囲と近代の伊参村の範囲とはどの程度重なり合うのか。また「いさま」が自然地形に由来する地名だとすれば、由来となった地形は伊参村に含まれるのかどうか。本当はそういう考証を経た上で新村名を決めてほしかった。
大いに評価できる伊参村の名にさえこういう問題がある。市町村合併のさなかにある現在、面妖な新地名の誕生も珍しくない。地名は文化財であることを念頭に、大局的な見地から新市町村名を決めてもらいたい。平成の新地名が後世、笑いものにならないように。(群馬県立女子大学教授)
きたがわ・かずひで 東京都出身。学習院大卒。同大学院人文科学研究科修了。学習院大助手を経て、県立女子大学へ。国語学・国文学専攻。現在、同大教授。著書に「群馬の万葉歌」など。
東西南北の方言が交差
篠木れい子

パンフレット
「群馬学の確立にむけて 第1号」
(群馬県立女子大学発行)
私たちは、谷川俊太郎のことばを借りれば「十ヶ月を何千億年もかけて生きて」この日本に、群馬に、誕生した。私たちの日々の生は、"今・ここ"群馬で展開している。考えてみれば、何とも不思議なことであり、運命的なことであると思われてならない。
ところで、私たちは、母親の胎内にある時からすでに、自分の母語となる地域のことばを学びはじめる。14、5歳にはその骨組みがすっかりできあがり、そのことばで私たちは世界をとらえている。豊かな感情も、共感する力、想像する力もこれによって培われるという。このことを思う時、人びとが日々の生活の中で紡いできた生活語である方言には、この地に生きた人びとの心がどれほど秘められていることか。というわけで、いずれの方言も魅力的であるが、群馬の方言はこの地に生きる私にとっては特別。しかも、方言研究者としての私にとっても特別魅力的である。
群馬の方言は、リズミカルで歯切れよく、江戸語的な特徴をいくつも留めている。また時に、新潟的な特徴も見られる。そればかりではない。東西の方言は大きな違いがあり、その境界線は日本アルプスが造り出した大地溝帯に集中することはよく知られているが、それよりかなり東に位置するにもかかわらず、群馬には東日本的なものと西日本的なものとのいずれもが見られるのである。連続している世界を分けて分類している基本的な単位は語である。群馬の西部山間部で用いられているその方言語彙がどのような分布を示しているかを見てみると、東日本に勢力をもつ語あり、西日本に勢力をもつ語あり。しかも、これらの地域は、その語が分布する南端であり、北端であることがほとんどであった。東と西が、北と南が、長い歴史の中で、この群馬の地で出会い、交わり・・・。多くの方々の研究成果に支えられながら、群馬の地で展開した行き交う人びと・行き交うことばに、そして、それを可能にしたいくつもの峠に、思いを馳せている。明日の私たちを思いつつ。(群馬県立女子大学教授)
足元固め、世界を見て
富岡 賢治

群馬学連続シンポジウム(第3回)の模様
県立女子大学は、語学教育の大幅な拡充、年間百人以上の留学の実現、新しい国際コミュニケーション学部の開設など国際化時代に自立ができる女性を育てようと、種々の改革を進めている。
その中で、学生が将来国際社会に出ていくためには、語学だけではなく、日本の文化や言葉もしっかり学ぶようにし、あわせて足元の群馬についても沢山勉強してもらおうではないかと我々は考えた。
教員たちも各々の専門分野から見ても群馬は実に興味深いところだと言う。言語学的に見ても群馬は日本の東西南北の言語のクロス点で独特の興味深い言語体系がある。万葉集の時代から現代まで短詩型文学が脈々と栄えてきたのはなぜか、質量とも奈良をも圧倒するほどの遺跡の由来は何か等々、改めて群馬をさまざまな角度からとらえ直す知的結集、つまり群馬学の確立を図りたいという機運が盛り上がった。
昨年、三度のシンポジウムを毎回七百人もの県民の参加も得て大学で開催した。多分野の専門家や経済人をパネリストに、群馬の特質をさまざまな角度から討議していただいた。共通のキーワードが出てきた。群馬は異文化共存の開放型社会だいう点である。気候や地理的な状況も背景の一つである。中山道、三国街道や利根川水運などの滞在型の交通の要地の故に異文化が自然と共存するようになったことも理由に挙げられた。近世史における強大な藩主の欠如による割拠分立の社会であったがための異文化共存であったこと、養蚕業を中心とした現金商売の流通経済により異文化共存で開放型社会が形成されたとする意見などが共通に語られた。このような識論で我々の群馬を解明していくのは実に楽しい企てであった。
我々がよりよい群馬にしてためには、ルーツを辿り、地域を見つめ直し、我々が誇るべき特質は何かを皆で考えていく事が必要である。おりしも全国いたるところで地域の文化発信ということが言われるようになった。その前に発信すべきものは何かの考察が不可欠だと思うのだ。(群馬県立女子大学長)